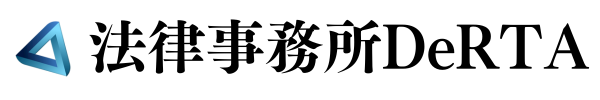遺言における「法定遺言事項」と「付言事項」とは?

遺言書を作成する際、法的に効力を持つ「法定遺言事項」と、法的拘束力はないものの故人の意思を伝える「付言事項」を理解することは非常に重要です。本記事では、遺言における両者の違いと具体的な内容について詳しく解説します。
法定遺言事項と付言事項の違い
法定遺言事項とは、民法などの法律によって遺言で定めることができると規定されている事項です。これらは法的拘束力を持ち、相続人や関係者を法的に拘束します。他方で、付言事項とは、遺言者の思いや希望を記載する事項で、法的な拘束力は持ちません。相続人や関係者に対するメッセージや、財産の使い方に関する希望などを記載します。
上記のとおり、最も重要な違いは「法的拘束力」(いわば強制力)の有無です。法定遺言事項は法的効力を持ち、相続人や関係者を法的に拘束します。一方、付言事項は法的拘束力はなく、道義的・倫理的な拘束力のみを持ちます。
法定遺言事項の例:「不動産Aは長男Bに相続させる」(法的に拘束力あり) 付言事項の例:「不動産Aは家族の集まる場所として大切にしてほしい」(法的拘束力なし)
法定遺言事項の具体例
法定遺言事項は、上記のとおり、民法などの法律によって遺言で定めることができると規定されている事項で、法的拘束力を持ち、相続人や関係者を法的に拘束します。法定遺言事項は、①相続に関する事項、②相続以外による遺産の処分に関する事項、③身分関係に関する事項、④遺言執行者に関する事項、⑤その他の事項の5つに分類できます。遺言書にこれらの事項を定めた場合、法的拘束力があります。
Ⅰ 相続に関する事項
① 推定相続人の廃除,廃除の取消し(民法893条・894条2項)
推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った場合など、相続人としてふさわしくない行為があった場合に、その相続人の相続権を奪うことができます。また、一度廃除した推定相続人の廃除を取り消すこともできます。
具体例:「長男Aは、私に対して長年にわたり暴言を吐き続け、虐待行為を行ってきたため、民法893条に基づき相続人から廃除する」
② 相続分の指定・指定の委託(民法902条)
法定相続分と異なる割合で相続財産を分ける場合に、各相続人の相続分を指定することができます。また、第三者に相続分の指定を委託することも可能です。
具体例:「長男Aの相続分を4分の2、次男Bの相続分を4分の1、長女Cの相続分を4分の1とする」 「相続分の指定については、私の信頼する弁護士Dに委託する」
③ 特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
生前贈与や婚姻・養子縁組のための贈与など、特別受益を受けた相続人に対して、本来なら相続時に持ち戻すべき財産の持戻しを免除することができます。
具体例:「長女Cに対して行った2,000万円の結婚資金の贈与については、民法903条3項に基づき、持戻しを免除する」
④ 遺産分割方法の指定・指定の委託,遺産分割の禁止(民法908条)
遺産の分割方法を具体的に指定したり、第三者に分割方法の指定を委託したりできます。また、一定期間(5年を超えない範囲)遺産分割を禁止することも可能です。
具体例:「東京都〇〇区〇〇町1-2-3の不動産は長男Aに、預金口座(〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号123456)は次男Bに、有価証券は長女Cに相続させる」 「私の死後3年間は遺産分割を禁止する」
⑤ 配偶者居住権の設定(民法1028条1項2号)
配偶者が亡くなった後も、残された配偶者が自宅に住み続けることができる権利(配偶者居住権)を設定することができます。
具体例:「東京都〇〇区〇〇町1-2-3の不動産について、妻Eに配偶者居住権を遺贈する。居住権の存続期間は妻Eの終生とする」
⑥ 遺留分侵害額の負担の割合の指定(民法1047条1項2号ただし書)
遺留分を侵害した場合に、遺留分侵害額を負担する割合を受遺者や受贈者の間で指定することができます。
具体例:「遺留分侵害額が生じた場合、その負担割合は長男Aが60%、友人Fが40%とする」
Ⅱ 相続以外による遺産の処分に関する事項
① 遺贈(民法964条)
遺言者が特定の財産を相続人以外の第三者に贈与することを指定できます。また、相続人に対しても特定の財産を取得させたい場合に遺贈を行うことができます。
具体例:「東京都〇〇区〇〇町4-5-6の不動産を友人Fに遺贈する」 「愛用の腕時計(ロレックス、シリアルナンバー123456)を甥のGに遺贈する」
② 信託の設定(信託法2条2項2号・3条2号)
遺言により財産の管理・処分を受託者に委ね、その利益を受益者に与える信託を設定することができます。
具体例:「私の所有する〇〇株式会社の株式1,000株について、信託銀行Hを受託者、孫Iを受益者とする信託を設定する。受託者は、信託財産から生じる配当金を孫Iが大学を卒業するまで管理し、教育資金として提供するものとする」
Ⅲ 身分関係に関する事項
① 認知(民法781条2項)
婚姻関係にない男性が、自分の子であることを認める認知を遺言で行うことができます。
具体例:「〇年〇月〇日生まれの〇〇〇〇(住所:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3)を、私の子として認知する」
② 未成年後見人の指定(民法839条1項)
親権者が亡くなった場合に、未成年の子の後見人を指定することができます。
具体例:「私の死後、未成年の子Jの後見人として、私の姉Kを指定する」
③ 未成年後見監督人の指定(民法848条)
未成年後見人を監督する未成年後見監督人を指定することができます。
具体例:「私の死後、未成年の子Jの後見監督人として、弁護士Lを指定する」
Ⅳ 遺言執行者に関する事項
① 遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条1項)
遺言の内容を実現するための手続きを行う遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
具体例:「本遺言の執行者として、弁護士M(〇〇弁護士会所属、事務所所在地:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3)を指定する」 「本遺言の執行者の指定は、〇〇司法書士事務所の司法書士Nに委託する」
Ⅴ その他の事項
① 祭祀承継者の指定(民法897条1項ただし書)
墓や仏壇など、祖先の祭りに関する権利を承継する人を指定することができます。
具体例:「〇〇家の墓(〇〇霊園第〇区第〇号)及び仏壇の祭祀承継者として、長男Aを指定する」
② 遺言の撤回(民法1022条)
先に作成した遺言の全部または一部を撤回することができます。
具体例:「〇年〇月〇日に作成した遺言のうち、長男Aに関する部分を撤回する」 「〇年〇月〇日に作成した遺言を全て撤回する」
付言事項の具体例
付言事項は、法的な拘束力はないものの、遺言者の思いや希望を記載する事項です。相続人や関係者に対するメッセージや、財産の使い方に関する希望などが含まれます。
付言事項の具体例
① 相続人へのメッセージ
遺言者の思い出や感謝の気持ち、人生観、相続人への期待などを伝えることができます。
具体例:「子供たちへ。長い間、共に歩んでくれてありがとう。あなたたちが幸せに暮らしていくことが私の最大の願いです。争いごとなく仲良く暮らしてください」 「妻へ。長年にわたり支えてくれて感謝しています。残された時間を自分のために使い、幸せに過ごしてください」
② 葬儀・埋葬に関する希望
葬儀の形式や埋葬方法、お墓の希望などを伝えることができます。法的強制力はありませんが、遺言者の最後の希望として尊重されることが多いです。
具体例:「葬儀は家族葬で、質素に執り行ってください。花は白いユリのみで飾ってください」 「私の遺体は火葬し、遺灰は〇〇海岸に散骨してください」
③ 財産の使途に関する希望
遺産の使い方についての希望(例:「教育資金として使ってほしい」「家業の継続に役立ててほしい」など)を伝えることができます。
具体例:「長男Aに相続させる事業用資産については、会社の発展のために活用してほしい」 「孫たちの教育資金として、各人に相続させる預金の一部を使ってほしい」
④ ペットの世話に関する希望
ペットの世話を誰にお願いしたいか、どのように世話をしてほしいかなどの希望を伝えることができます。
具体例:「愛犬ポチの世話は長女Cにお願いしたい。ポチは毎日の散歩を楽しみにしているので、可能な限り続けてあげてほしい。また、かかりつけの〇〇動物病院で年に一度健康診断を受けさせてほしい」
⑤ デジタル遺品の取り扱い
SNSアカウントやデジタルデータの取り扱いについての希望を伝えることができます。
具体例:「私のSNSアカウント(Facebook、Twitter、Instagram)は、死後に削除してほしい。ただし、写真データは家族の思い出として保存してほしい」 「クラウドストレージに保存している家族写真は、全ての子供たちでシェアしてほしい」
⑥ 寄付に関する希望
財産の一部を寄付することへの希望を伝えることができます。
具体例:「私の遺産の一部を〇〇大学の奨学金制度に寄付してほしい」 「環境保護活動をしている〇〇団体に100万円を寄付してほしい」

法定遺言事項と付言事項を組み合わせた実際の遺言例
第1条(遺産分割方法の指定)
私の所有する以下の財産について、相続人に対し以下のとおり相続させる。
1. 東京都〇〇区〇〇町1-2-3の土地建物は、長男Aに相続させる。
2. 〇〇銀行〇〇支店普通預金(口座番号123456)の預金は、次男Bに相続させる。
3. 〇〇証券の有価証券(口座番号789012)は、長女Cに相続させる。
第2条(特別受益の持戻し免除)
私が長女Cに対して行った結婚資金2,000万円の贈与については、民法903条3項に基づき、持戻しを免除する。
第3条(遺贈)
私の所有する愛用の腕時計(ロレックス、シリアルナンバー123456)を甥のDに遺贈する。
第4条(遺言執行者の指定)
本遺言の執行者として、弁護士E(〇〇弁護士会所属、事務所所在地:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3)を指定する。
第5条(付言事項)
1. 子供たちへ。長い間、共に歩んでくれてありがとう。あなたたちが幸せに暮らしていくことが私の最大の願いです。争いごとなく仲良く暮らしてください。
2. 長男Aに相続させる不動産は、できれば家族の集まる場所として大切にしてほしい。
3. 葬儀は家族葬で、質素に執り行ってください。
4. 愛犬ポチの世話は長女Cにお願いしたい。ポチは毎日の散歩を楽しみにしているので、可能な限り続けてあげてほしい。
令和〇年〇月〇日
氏名:〇〇〇〇 (自筆署名)
遺言書作成時の注意点
- 法定遺言事項と付言事項を明確に区別する:混同すると法的効力に影響を与える可能性があります。法定遺言事項には「相続させる」「遺贈する」などの明確な表現を使い、付言事項には「希望する」「お願いしたい」などの表現を使うと良いでしょう。
- 専門家に相談する:遺言書の作成には法律の専門知識が必要です。弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に財産が多い場合や、相続関係が複雑な場合は必須と言えるでしょう。
- 定期的な見直し:財産状況や家族構成の変化に応じて、定期的に遺言書の内容を見直しましょう。結婚、離婚、出生、死亡などの家族状況の変化や、財産の取得・処分があった場合は特に重要です。
- 遺言書の保管:自筆証書遺言の場合、法務局での保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができます。公正証書遺言の場合は、公証役場で原本が保管されます。
- 相続税の考慮:遺言内容によっては相続税の負担が変わることがあります。税理士等の専門家に相談し、税負担を考慮した遺言書を作成することも大切です。
まとめ
遺言における法定遺言事項と付言事項を正しく理解し、適切に遺言書を作成することで、相続トラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に実現することができます。特に法定遺言事項は法的効力を持つため、正確に記載することが重要です。一方、付言事項は法的拘束力はないものの、遺言者の思いを伝える大切な手段となります。
遺言書の作成は、単なる財産分与の指示だけでなく、最後のメッセージを伝える大切な機会でもあります。法的効力のある内容と、思いを伝える内容をバランスよく盛り込んだ遺言書を作成しましょう。具体例を参考にしながら、自分自身の状況に合った遺言書を作成することをお勧めします。
当事務所では「遺言」のご相談を承っております。「遺言」についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所(法律事務所DeRTA(デルタ))にご相談ください。
併せて読みたいオススメ記事