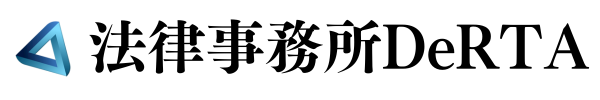対話で理解する「任意後見」の基礎

私たちは誰しも年を重ねていく中で、いつまでも健康で自分の意思決定ができる状態が続くことを望んでいます。しかし、高齢化社会の進展とともに、認知症など判断能力が低下する可能性についても考えておく必要があります。
そんな将来への不安に対して、日本の法制度では「任意後見制度」という仕組みが用意されています。この制度は、判断能力があるうちに将来の備えをしておくことで、自分らしい生活を守るための大切な選択肢となります。
今回は、この「任意後見制度」について、よくある疑問を対話形式でわかりやすく解説していきます。将来の安心のために、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
任意後見とは?
任意後見制度とはどんな制度?
皆さんこんにちは!今日は「任意後見制度」について、弁護士の先生にお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いします。
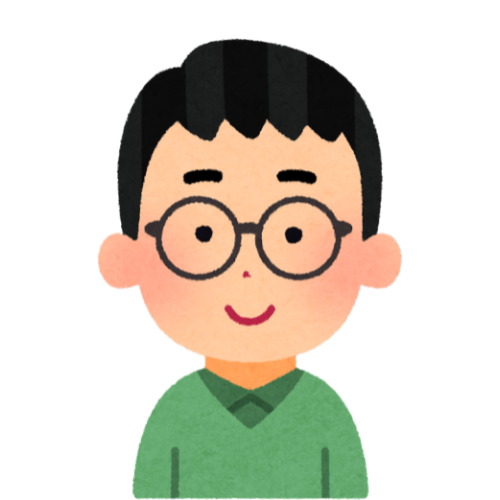
こんにちは。今日は皆さんの将来の安心のために役立つ「任意後見制度」についてお話しします。

まず基本的なところから教えていただきたいのですが、「任意後見」って何なんでしょうか?
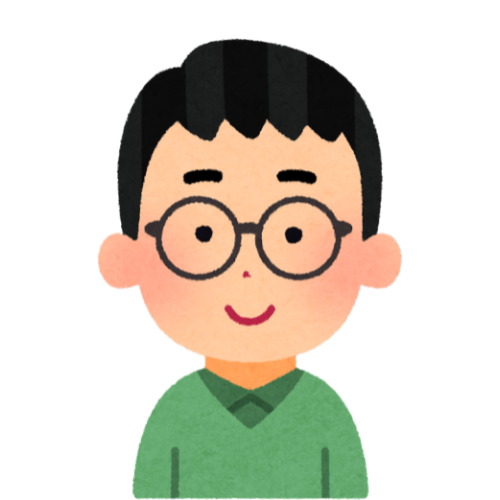
簡単に言うと、「将来、自分で判断することが難しくなったときのために、信頼できる人に自分の代わりに色々なことをお願いしておく制度」です。例えば、認知症になったときに、銀行での手続きや不動産の管理などを、自分が選んだ人にお願いできるんです。

なるほど!つまり、元気なうちに「もしものとき」の準備をしておくということなんですね。それは公的な制度なんですか?
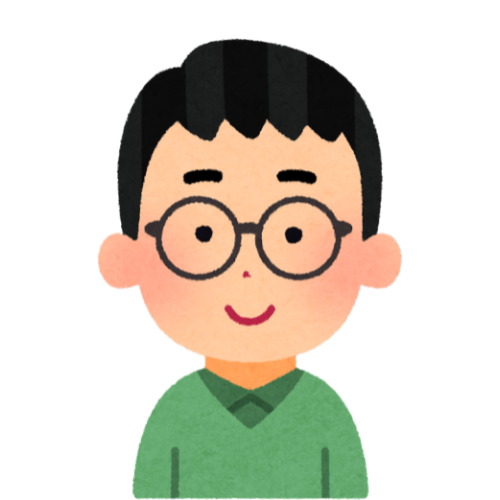
はい、民法で定められた正式な制度です。公正証書という法的な文書で契約を結びます。だから、しっかりと法律で保護された形で将来に備えることができるんですよ。

公正証書で契約するんですね。実際にそれが効力を発揮するのはどういうときなんでしょう?
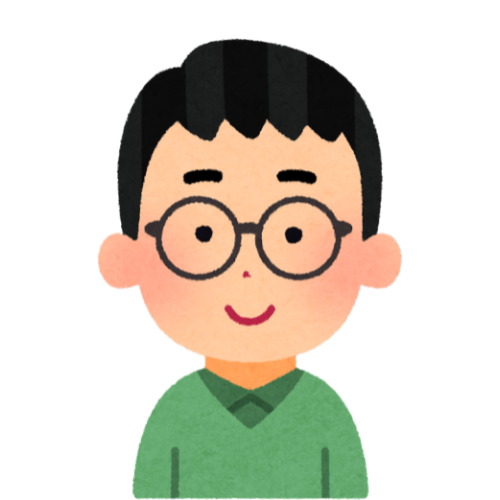
それが重要なポイントです。任意後見契約を結んだだけでは、すぐに効力は発生しません。実際に認知症などで判断能力が低下したと判断されたとき、家庭裁判所に申立てをして「任意後見監督人」という人が選任されることで、初めて効力が発生するんです。それまでの間は、見守り契約や財産管理契約で関わることになることが多いです。

任意後見契約を結んでいなかったら?
なるほど!じゃあ、もし「任意後見契約」を結んでいなかったら、何か困ることはあるんですか?
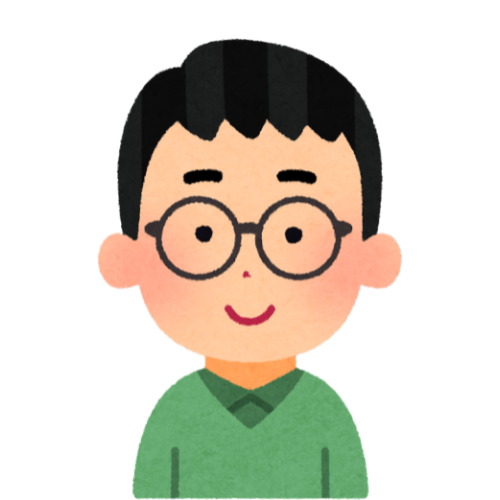
そうですね、例えば認知症になると、銀行口座が凍結されて生活費が引き出せなくなったり、必要な介護サービスを自分で契約できなくなったりするんです。また、不動産を所有している場合にも管理や処分ができなくなってしまいます。

銀行口座が凍結されるというのは、具体的にどういう状況なんですか?
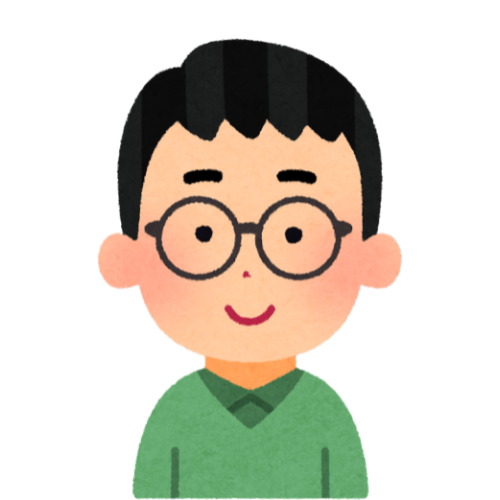
認知症になってしまうと取引が無効になってしまうため、銀行側が取引を制限することがあるんです。特に高額な引き出しや解約などは難しくなります。認知症の症状が進行すると、暗証番号を忘れたり、ATMの操作ができなくなったりすることもありますよね。

なるほど。そうなったら、家族が代わりに手続きすることはできないんですか?
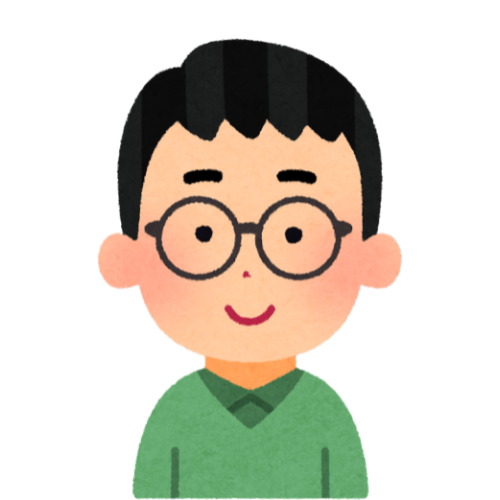
実は、家族だからといって自動的に代理権が発生するわけではないんです。例えば、配偶者であっても、法的な代理権がなければ本人の銀行口座からお金を引き出すことはできません。だから、何も準備していない状態で認知症になると、日常生活に必要なお金の管理さえ難しくなるんですよ。

任意後見契約でできることとは?
それは心配ですね…。では反対に、任意後見を結んでおくとどんなことができるようになるんですか?
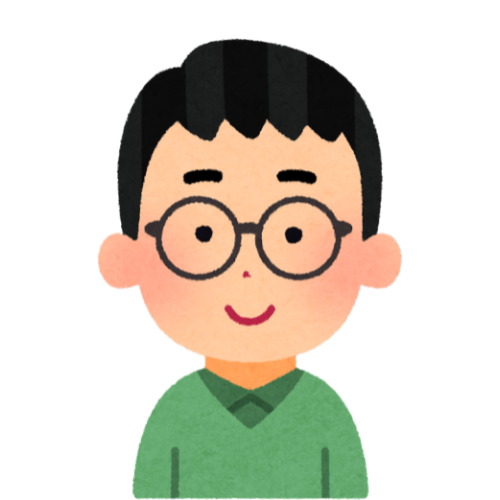
一番大きいのは「自分の将来のあり方を自分で決めることができることです。まずは自分で後見人を選べますし、「この預金はこう使ってほしい」「自宅での生活をできるだけ続けたい」など、細かい希望を伝えておくこともできますよ。認知症になっても自分らしい生活を続けることが可能になります。

具体的にはどんなことをお願いできるんでしょうか?例えば趣味や娯楽にお金を使うことも頼めますか?
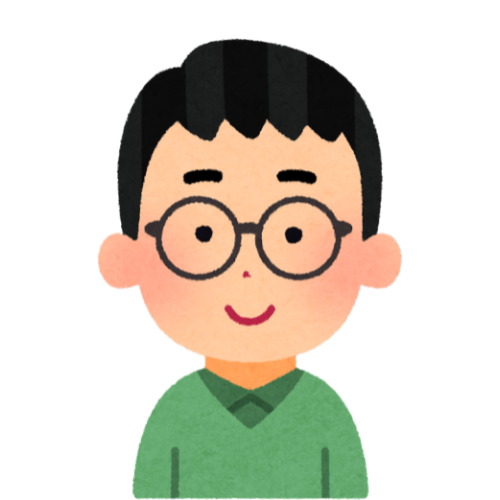
もちろんです。「週に一度は好きな音楽コンサートに連れて行ってほしい」「俳句の会には継続して参加させてほしい」といった趣味に関することも契約内容に含めることができますよ。また、「親しい友人との交流を続けたい」「ペットと一緒に暮らしたい」といった生活スタイルに関する希望も伝えておけます。つまり、財産管理だけでなく、生活の質を維持するための細かい希望も盛り込むことができるんです。

それは安心ですね。自分の人生の後半も、自分らしく過ごせるようにできるわけですね。
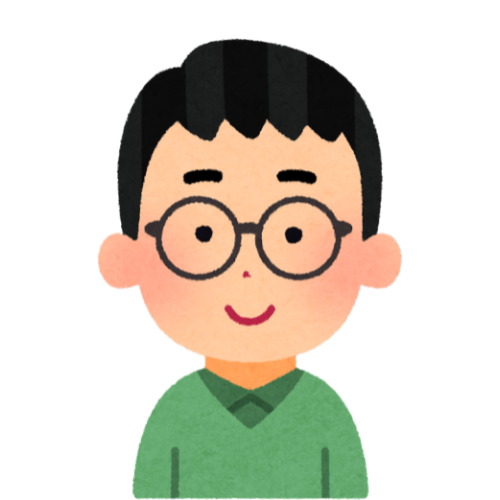
そうです。これが任意後見制度の最大の特徴で、「自己決定権の尊重」と言われるものです。自分の生き方や価値観を尊重した支援を受けられるように、事前に準備しておくことができるんです。

法定後見で十分では?任意後見の必要性

でも、認知症になってから法定後見を申し立てれば良いんじゃないですか?
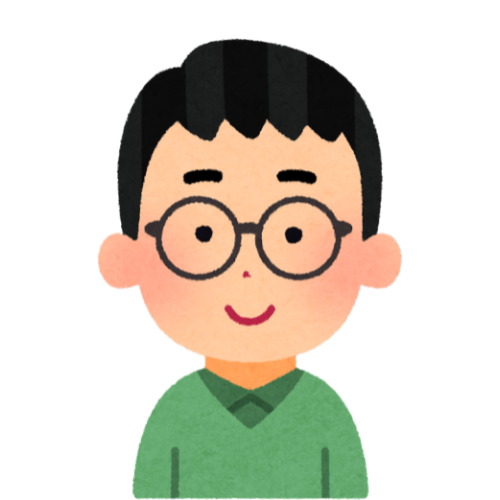
それも一つの選択肢ですが、認知症になってからでは自分の希望を十分に伝えられなくなっていますし、裁判所が選ぶ後見人が必ずしもあなたの希望する人とは限らないんです。また、現在の実務では後見人が本人に合った柔軟な対応をすることは困難という問題があります。

法定後見と任意後見の違いをもう少し詳しく教えていただけますか?
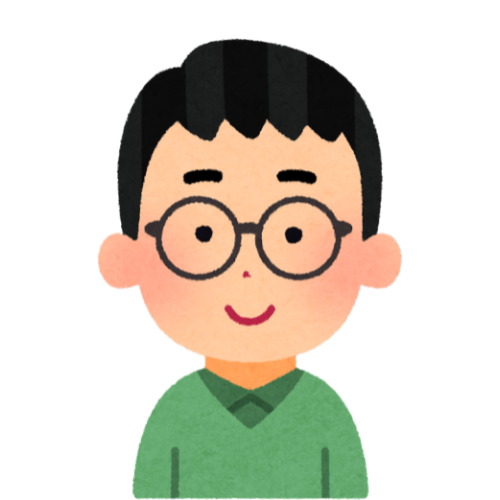
最大の違いは「いつ、誰が決めるか」ということです。任意後見は「判断能力があるうちに、自分で後見人と内容を決める」のに対して、法定後見は「判断能力が低下した後に、家族などが申し立てて、裁判所が後見人を決める」という違いがあります。また、法定後見では基本的に「本人保護」が最優先されるため、リスクを避ける観点から財産管理が行われることが多く、例えば「趣味にお金を使う」「家族に援助する」といったことが制限される可能性があります。つまり、自分らしい生活を続けるという点では、任意後見の方が自由度が高いと言えるでしょう。

任意後見のデメリットとは?
なるほど、事前に準備しておく意味があるんですね。ところで、任意後見にもデメリットはあるんでしょうか?
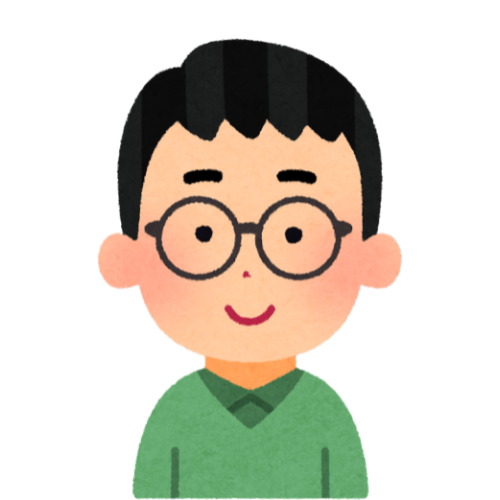
(B)はい、一番のデメリットは、公正証書作成費用や後見人への報酬などの費用がかかる点です。

費用はどのくらいかかるものなんですか?
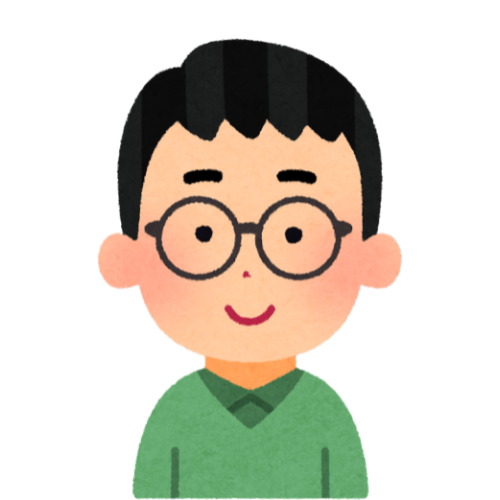
まず、公正証書の作成費用として2万円程度かかります。そして、任意後見が実際に始まると、任意後見監督人への報酬として月額2万円程度、任意後見人への報酬として月額3万円から5万円程度が一般的です。ただし、財産の規模や管理の複雑さによって変わりますし、親族が任意後見人になる場合は報酬を低く設定することも考えられます。

任意後見人をどうするか?

任意後見人は誰がなれるか?
確かに費用面は考慮が必要ですね。ところで、任意後見人は、どんな人がなれるんですか?家族じゃないとダメなんでしょうか?
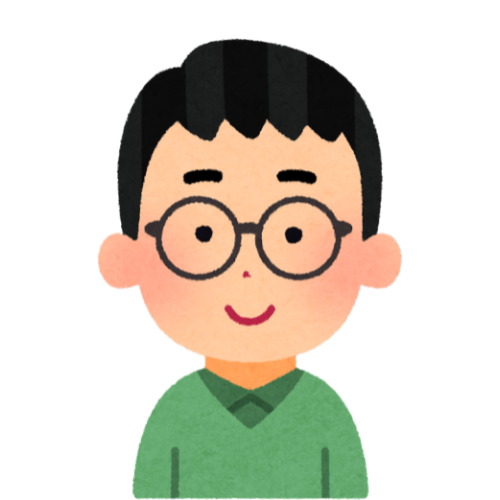
基本的には、あなたが信頼できる人なら誰でもなれますよ。家族や親族はもちろん、親しい友人や、弁護士などの専門家、さらには法人を選ぶこともできます。大事なのは、あなたの意思を尊重してくれる人、財産管理能力がある人を選ぶことですね。

なるほど。親族と専門家、両方に任意後見人になってもらうことはできるんですか?
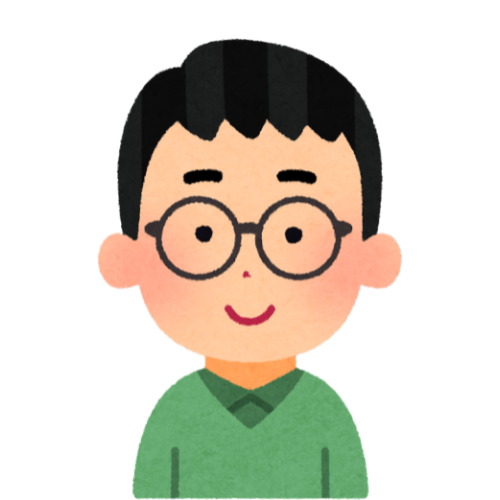
はい、複数の人を任意後見人に指定することもできますし、それぞれの役割分担を決めておくこともできます。例えば、財産管理は弁護士に、身上監護(日常生活の支援)は親族に、というように分けることも可能です。ただし、複数の後見人の間で意見が対立する可能性もあるので、役割分担は明確にしておくことが大切です。

弁護士を任意後見人に選任するメリットとは?
最後に、弁護士さんに任意後見人になってもらう必要はあるんでしょうか?
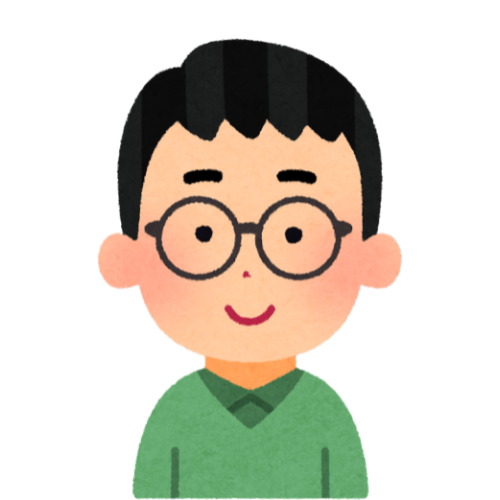
「必要」というわけではないですが、複雑な財産管理が必要な場合や、家族間に対立がある場合などは、専門家である弁護士が役立つことも多いですね。また、親族と弁護士で役割分担するという方法もありますよ。財産管理は弁護士、日常生活のサポートは家族というように、ベストな組み合わせを考えるといいでしょう。

弁護士さんを選ぶメリットって具体的にどんなことがあるんでしょう?
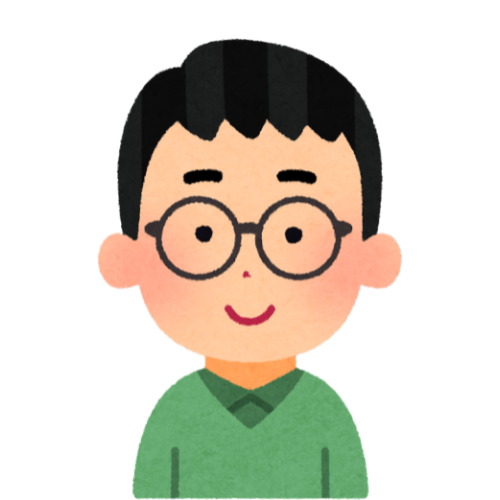
最大のメリットはあらゆる法的な問題に対応できることです。まず、法律の専門家ですから、不動産や株式などの複雑な財産管理、契約書の確認、各種手続きなどを正確に行うことができます。そして、職業として後見業務を行うので、親族のような感情的な判断に左右されにくいという面もあります。さらに、弁護士には守秘義務があるので、財産状況などのプライバシーを守りたい方にも安心です。ただし、日常的な見守りやきめ細かなケアは、身近にいる親族の方が対応しやすい面もあるので、状況に応じた選択が大切ですね。

なるほど、財産が複雑だったり、家族関係に課題があったりする場合は、弁護士さんの力を借りる価値がありそうですね。弁護士であれば誰でもいいのですか?
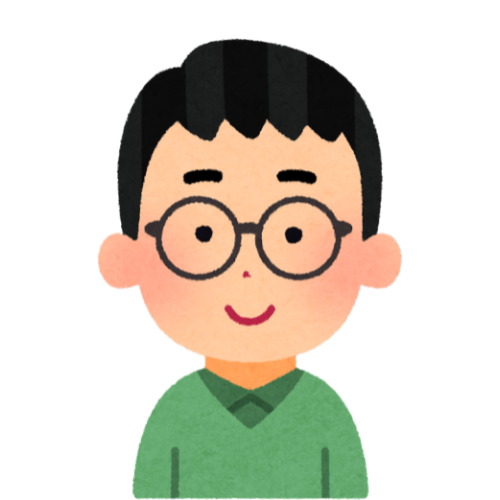
弁護士でも任意後見を扱っていない方、扱っていても力を入れていない方もいるので確認する必要はありますね。いずれにせよ、大切なのはご自身の状況や希望に合った最適な任意後見人を選ぶことです。迷ったときは、ぜひ弁護士などの専門家に相談してみてください。

今日は任意後見について、とても分かりやすく教えていただきありがとうございました!皆さんも、お元気なうちに将来の安心のために、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
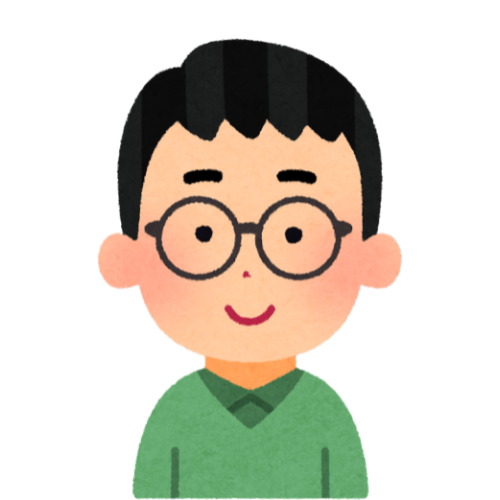
任意後見制度の導入をご検討中の方は、お気軽に法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。
当事務所では、任意後見・遺言・死後事務委任等に関する初回相談を無料で承っております。認知症対策、相続対策、事業承継対策など、あなたの悩みに合わせた最適なプランをご提案いたします。「任意後見」についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
早めの準備がトラブルを防ぎます。あなたの大切な生活を守るための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
併せて読みたいオススメ記事