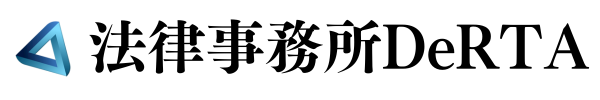【弁護士が解説】デジタル遺品の問題と対策|生前から備える重要性(死後事務委任等の活用)

近年、インターネットやスマートフォンの普及に伴い、故人が残した「デジタル遺品」の問題が注目されています。
本記事では、デジタル遺品とは何か、発生し得る問題点、対策を怠った場合のリスク、事前にできる具体的な対策について、弁護士の立場から詳しく解説します。
1.デジタル遺品とは
デジタル遺品とは、亡くなった方が生前に利用していたスマートフォン、パソコン、クラウドサービス、SNSアカウント、ネットバンキング、仮想通貨、電子書籍、写真データなど、電子データやデジタル機器に保存された財産や記録全般を指します。
生前の生活の多くがデジタル化された現代では、相続財産に占めるデジタル遺品の割合が年々高まっており、適切な対応が求められるようになっています。
2.デジタル遺品の問題点(国民生活センターの相談事例)
デジタル遺品に関するトラブルは年々増加しています。
国民生活センターの令和6年11月20日付「今から考えておきたい『デジタル終活』-スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-」によると、以下のような相談事例が寄せられています。
【事例1】故人が利用していたネット銀行の手続きをしたくてもスマホが開けず、ネット銀行の契約先がわからない
【事例2】コード決済サービス事業者の相続手続きが1か月以上たっても終わらない
【事例3】故人が契約したサブスクの請求を止めたいが、IDとパスワードがわからない
相談の背景としては、
- 故人のスマホやパソコン等のパスワードがわからない場合、第三者がロック解除することは困難
- ネット上の資産は本人以外が実態を把握することが難しく、相続手続きに時間がかかることがある
- サブスクは解約手続きをしない限り請求が続いてしまう
ということが挙げられています。
上記は一例にすぎず、デジタル遺品の管理が不十分な場合、遺族にとって大きな負担となる可能性があります。
3.デジタル遺品の対策をしないとどうなるか
デジタル遺品の管理や整理を行わずにいると、データ等にアクセスできない結果、以下のようなリスクが発生します。
- 財産の喪失:ネットバンキングや仮想通貨口座にアクセスできず、財産を相続できない。
- 無駄な出費:サブスクリプションサービスや各種契約の解約漏れによる不必要な支出。
- プライバシー侵害:故人の個人情報が第三者に漏洩し、悪用される危険性。
特に、仮想通貨や電子マネーのように実体のない財産については、アクセス情報がなければ実質的に回収不能となるため、注意が必要です。
データ等にアクセスできない場合、
- 故人によるバックアップデータにアクセスし、バックアップ時のデータを復元する方法
- データ復旧専門家に依頼し、ログインパスワード解除等を依頼する方法
が考えられますが、①については故人がバックアップしていることが前提であるうえ、バックアップ先等の情報を把握していることが必要であり、②については高額な費用(20万円〜50万円程度)がかかるうえ、期間も1年以上に亘るケースもあり、また、対応不可の機種などもあって、半数以上がデータ復旧を諦めている実情があるとされています。
4.デジタル遺品の対策(死後事務委任等)

デジタル遺品に関するトラブルを未然に防ぐためには、事前の対策が不可欠です。そこで、以下のような対策が有効です。
1.リストの作成と保管
- 主要なアカウント(ネットバンキング、SNS、クラウドサービスなど)のID・パスワード一覧を作成し、信頼できる方法で保管する。
- 利用中のサービス名や支払方法も明記しておくと、解約手続きがスムーズになります。
2.遺言書やエンディングノートの活用
- 遺言書にデジタル遺品の管理方針(削除・保存・移管など)を明示する。
- エンディングノートにアカウント情報や希望する取扱方法を記載しておく。
※遺言書は法的拘束力を持ちますが、エンディングノート自体には法的効力はありません。
重要な希望は遺言書に記載することを推奨します。
3.死後事務委任契約の締結(弁護士等に依頼)
⑴ 死後事務委任とは
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、あらかじめ第三者に依頼しておくための契約です。具体的には、
- 葬送に関する事務
葬儀・火葬・埋葬,供養・法要等 - 行政機関への届出等の手続
死亡届提出,年金の受給資格抹消申請,健康保険証の返還,運転免許証・旅券の返納,税金の納付等 - 生活に関する手続
関係者への死亡の連絡,病院や介護施設の未払料金の精算,賃貸不動産の解除・明渡,公共料金の支払・解約,インターネットの解約,SNS等のアカウント削除,PC・携帯電話の個人情報の抹消処理,ペットの引渡し・施設入所等
などが挙げられます。デジタル遺品の削除・整理も委任事項に含めることが可能です。
⑵ 死後事務委任を弁護士に依頼するメリット・デメリット
弁護士に死後事務委任を依頼するメリットとして、以下の事項が挙げられます。
- 法的な専門知識による確実な対応
弁護士は法律の専門家であり、デジタル遺品に関する法的な問題にも精通しています。例えば、SNSアカウントやオンラインサービスの解約、デジタル資産の相続手続きなど、複雑な事務も法的根拠に基づいて適切に処理できます。 - プライバシーの保護と信頼性
弁護士には守秘義務が課されており、故人のプライバシーや機密情報を厳格に守ります。デジタル遺品には個人情報やプライベートなデータが含まれることが多いため、信頼できる専門家に任せることで安心感が得られます。 - 相続人間のトラブル防止
弁護士が第三者として死後事務を行うことで、相続人間の感情的な対立やトラブルを未然に防ぐことができます。特に、デジタル遺品の価値や取り扱いに関して意見が分かれる場合でも、公正な立場で対応してもらえます。 - 他の制度との併用による柔軟な対応
弁護士は、遺言書の作成や信託契約など、他の制度との併用についてもアドバイスを提供できます。これにより、デジタル遺品の管理だけでなく、全体的な相続計画を立てることが可能です。
他方で、弁護士に死後事務委任を依頼するデメリットとして以下が挙げられます。
- 費用が発生する
弁護士に依頼する場合、報酬や手数料が発生します。費用は依頼内容や地域によって異なりますが、事前に見積もりを取得し、納得の上で契約を結ぶことが重要です。 - 信頼できる弁護士の選定が必要
死後事務委任は、故人の死後に発効する契約であるため、信頼できる弁護士を選定することが不可欠です。信頼関係を築くためにも、事前に面談を行い、対応や姿勢を確認することが望ましいです。
とはいえ、弁護士と死後事務委任契約を締結することで、秘密保持と適切な処理が保証され、遺族に無用な負担をかけずに済みます。
5.まとめ:デジタル遺品対策は生前からの準備(死後事務委任等)が重要
デジタル遺品は、放置すると大きなトラブルや財産損失を招く可能性があります。
スマートフォンやパソコンの中には、目に見えない重要な財産や個人情報が多く含まれているからです。生前からアカウント情報の整理、遺言書の作成、死後事務委任契約の締結などを進め、自身と大切な家族のために万全な対策を講じましょう。
法律事務所DeRTA(デルタ)では、デジタル遺品・死後事務委任に関する初回相談を無料で承っております。認知症対策、相続対策など、あなたの悩みに合わせた最適なプランをご提案いたします。「死後事務委任」についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
併せて読みたいオススメ記事