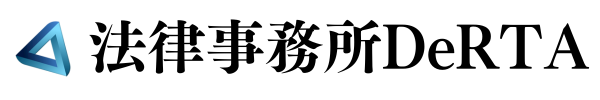任意後見を弁護士に依頼するメリットとは?制度の基礎と活用方法を解説

将来、認知症などで判断能力が低下してしまった場合に備えて、信頼できる人に財産管理や身上保護を託す「任意後見制度」。この制度を弁護士に依頼することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。本記事では、任意後見制度の基本的な仕組みから、弁護士に依頼する具体的な利点、さらには活用方法について詳しく解説します。
1.任意後見制度とは?弁護士が解説する制度の基本
まずは、任意後見制度がどのような制度で、なぜ今注目されているのか、その概要と社会的背景について見ていきましょう。
高齢化社会と後見制度の必要性
日本は急速に高齢化が進行しており、それに伴い認知症高齢者の数も増加傾向にあります。認知症などにより判断能力が不十分になると、ご自身での財産管理や契約行為、医療・介護サービスの手続きなどが困難になる可能性があります。このような状況に備え、本人の意思を尊重しながら生活を支援する仕組みとして、後見制度の重要性が高まっています。
後見制度には、すでに判断能力が低下した方向けの「法定後見制度」と、将来の判断能力低下に備える「任意後見制度」の2種類があります。特に任意後見制度は、本人が元気なうちに、将来支援してくれる人(任意後見人)や支援内容を自ら決定できる点で、自己決定権を尊重する現代のニーズに合致した制度と言えるでしょう。
任意後見の基本的仕組み
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受任者)に対し、自身の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくというものです。
そして、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、その任意後見契約の効力が生じます。任意後見人は、任意後見契約で定められた範囲内で、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しながら、財産管理や身上保護の事務を行います。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおり適正に仕事をしているかを監督する役割を担います。
上記のとおり、任意後見は、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来に備えて締結する契約です。多くの方は、認知症になったら法定後見(成年後見等)を申し立てればよいと考えがちですが、法定後見は自由度が低いので、必ずしも充分なサービスとは言えません。そこで、任意後見が重要となってきます。
2.任意後見契約と併用される制度(弁護士に依頼可)
任意後見契約は、判断能力が低下した後の支援に備えるものですが、それ以前の段階や、亡くなった後の手続きについても備えておきたいというニーズがあります。そのような場合、任意後見契約と併せて他の契約も検討することで、より包括的なサポート体制を築くことができます。
見守り契約・財産管理契約・死後事務委任
見守り契約:任意後見契約の効力が発生するまでの間、定期的な連絡や訪問を通じて本人の心身の状態や生活状況を見守り、必要な助言や支援を行う契約です。任意後見契約を締結しても、すぐに効力が発生するわけではないため、判断能力が低下する前から継続的な関わりを持つことで、スムーズな移行と安心感を得られます。
財産管理契約(任意代理契約):任意後見契約と同様に、本人が選んだ代理人に財産の管理を委任する契約ですが、こちらは本人の判断能力が低下する前から効力を発生させることができます。身体的な衰えなどにより、判断能力はしっかりしていても財産管理が難しくなってきた場合に活用できます。任意後見契約と一体的に締結されることも多く、「移行型」と呼ばれたりします。
死後事務委任契約:本人が亡くなった後の葬儀、埋葬、医療費や施設利用料の支払い、遺品整理などの事務手続きを委任する契約です。身寄りのない方や、家族に負担をかけたくない場合に利用されます。任意後見人の業務は本人の死亡によって終了するため、死後の手続きも依頼したい場合は別途この契約が必要です。
これらの契約を任意後見契約と組み合わせることで、判断能力があるうちから、判断能力が低下した後、そして亡くなった後まで、切れ目のないサポートを受けることが可能になります。
家族信託との違いと選択のポイント
家族信託は、本人が元気なうちに、特定の財産(例えば、自宅や収益物件など)の管理や承継を、信頼できる家族などに託す契約です。任意後見制度が本人の身上保護(生活や療養看護に関する事務)と財産管理全般を目的とするのに対し、家族信託は主に特定の財産の管理・運用・処分、そして円滑な承継に特化した仕組みであり、委託者の意向に沿った柔軟な財産管理が期待できる場合があります。
ただし、家族信託の受託者には原則として身上保護を行う権限はなく、また任意後見制度のような家庭裁判所による監督も通常ありません。そのため、生活全般にわたる支援や身上の配慮も必要とする場合は任意後見制度の利用が適しており、特定の財産の管理や承継を主目的とする場合には家族信託が有効な選択肢となります。両制度の特性を理解し、必要に応じて併用することも含め、専門家と相談しながらご自身の状況や希望に最も適した方法を選択することが重要です。

3.弁護士による任意後見の実務と他職種との比較
任意後見の担い手には、家族のほか、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職がいます。ここでは、特に弁護士に依頼するメリットや、他職種との違いについて解説します。
弁護士への依頼の可否
任意後見人となる者に制限はありません。ですので、弁護士に任意後見を依頼することは可能です(ただし、対応していない弁護士もいますので、事前に確認する必要があります。)。弁護士は法律の専門家であり、権利擁護や財産管理、紛争解決に関する高度な知識と経験を有しています。そのため、複雑な財産関係を持つ方や、将来的に親族間での意見対立が予想される場合など、法的なサポートが特に求められるケースにおいて、弁護士への依頼は有力な選択肢となります。
司法書士・行政書士との対応範囲の違い
司法書士や行政書士も任意後見の専門家として活動していますが、対応できる業務範囲に違いがあります。
- 行政書士:主に任意後見契約書の作成支援や相談業務を行います。ただし、代理人として交渉したり、法的な紛争が生じた場合の対応はできません。
- 司法書士:任意後見契約書の作成支援のほか、不動産登記手続きの代理など、財産管理に関する一部の法律事務を行うことができます。また、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理業務も可能です。
- 弁護士:任意後見契約に関する全ての法律事務(契約書作成、財産管理、身上保護、家庭裁判所への申立てなど)を代理人として行うことができます。特に、紛争が生じた場合の交渉や訴訟代理は弁護士の独占業務であり、他の職種では対応できません。
このように、弁護士は紛争処理経験も豊富であるうえ、最も広範な業務に対応できるため、将来的なトラブルの予防や、万が一紛争が発生した場合のスムーズな解決が期待できます。
弁護士による財産管理の信頼性
弁護士は、その職務の性質上、高い倫理観と責任感が求められます。弁護士法に基づき、依頼者の利益を最大限に守る義務を負っており、財産管理においても厳格な規律のもと業務を行います。弁護士会による監督指導もあり、不正行為や不適当な行為を行う場合には懲戒処分を課されます。また、多くの弁護士は弁護士賠償責任保険へ加入しており、これも信頼性を担保する要素と言えます。
トラブル時の対応力と責任体制
任意後見においては、本人の財産を狙った詐欺や、親族間での意見の対立、医療や介護に関する判断など、様々なトラブルが発生する可能性があります。
弁護士は、法律の専門家として、これらのトラブルに対して的確に状況を分析し、交渉や法的手続きを通じて解決を図ることができます。特に、訴訟に発展するような複雑な紛争においては、弁護士の対応力が不可欠です。
また、弁護士は職務上の過誤によって依頼者に損害を与えた場合に備え、弁護士賠償責任保険に加入していることが一般的です。これにより、万が一の場合にも依頼者の損害が補填される体制が整っています。
したがって、弁護士に任意後見を依頼することは、多くのメリットがあります。
4.任意後見を弁護士に依頼する前の確認事項
任意後見は長期間にわたる契約であり、信頼できる弁護士を選ぶことが非常に重要です。依頼前に確認すべきポイントをまとめました。
弁護士に依頼する際の基本的な流れ
- 相談予約:まずは法律事務所に連絡し、相談の日時を予約します。
- 初回相談:現在の状況、将来の希望、不安な点などを弁護士に伝えます。弁護士からは、任意後見制度の説明や、具体的な進め方、費用などについて説明があります。
- 方針決定・契約:弁護士からの提案内容に納得できれば、委任契約を締結します。
- 任意後見契約書の作成:弁護士と協議しながら、任意後見契約の内容(委任する事務の範囲、報酬など)を具体的に決定し、公正証書で作成します。
- 見守り契約等の締結(必要な場合):任意後見契約の効力発生前からサポートが必要な場合は、見守り契約や財産管理契約も併せて締結します。
- 任意後見監督人の選任申立て:本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
- 任意後見業務の開始:任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、弁護士(任意後見人)による業務が開始されます。
専門的な対応の有無
任意後見は、法律知識だけでなく、高齢者福祉や医療に関する理解も求められる分野です。また、任意後見を取り扱っていない法律事務所もあるので、以下の点を確認しましょう。
- 任意後見の専門的な対応の有無:任意後見を取り扱っておらず、また、取り扱っていても力を入れていない法律事務所も多くあります。専門的に取り扱っているか否かを確認する必要があります。
- 高齢者問題や相続案件の取り扱いの有無:任意後見だけではなく、周辺分野の取扱い実績があるか否かも考慮すべきです。なぜなら、任意後見を行ううえで周辺分野の法律問題も関わってくる可能性があるからです。
- 身上保護に関する理解:財産管理だけでなく、本人の生活や療養看護に関する配慮や知識があるか否かも確認する必要があります。事務的な作業を行うのみの方ではなく、親身になって配慮してくれる方を探す必要があります。
サービスの内容・範囲
任意後見と一口に言っても、弁護士によって提供するサービスの内容や範囲が異なる場合があります。
- 定期的な報告:財産状況や業務の遂行状況について、どの程度の頻度で、どのような形で報告してくれるか。
- 身上保護の具体的な対応範囲:介護サービスの契約締結、入院手続き、住環境の整備など、どこまで対応してくれるか。
- 緊急時の対応体制:休日や夜間など、緊急時の連絡体制や対応について確認しましょう。
- 身元保証の可否:入院等の際に身元保証人となってくれるか(「身元保証」の内容も様々なので注意が必要です。)。
費用の内訳・支払方法
費用についても事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
- 相談料:初回相談が無料か有料か。
- 任意後見契約公正証書作成費用:実費(公証人手数料など)のほか、弁護士への手数料はいくらか。
- 任意後見人への報酬:月額でいくらかかるのか。財産額や業務内容によって変動するのか。
- 任意後見監督人への報酬:家庭裁判所が決定しますが、目安を教えてもらえるか。
- 実費:交通費や通信費など、別途かかる費用はあるか。
- 支払方法:一括払いか分割払いか、支払いのタイミングはいつか。
複数の法律事務所から見積もりを取り、比較検討することも有効です。ただし、費用だけで選ぶのではなく、信頼性や専門性も総合的に判断することが大切です。
5.まとめ|任意後見は信頼できる弁護士への依頼が安心

任意後見制度は、将来の不安に備え、自分らしい生活を守るための有効な手段です。特に弁護士に依頼することで、法律に基づいた適切な財産管理や権利擁護が期待でき、複雑な問題や万が一のトラブルにも的確に対応してもらえるという大きな安心感が得られます。
任意後見契約は長期間にわたる重要な契約です。ご自身の希望や状況をしっかりと理解し、親身になって相談に乗ってくれる、信頼できる弁護士を見つけることが何よりも大切です。早めに準備を始めることで、より安心して将来を迎えることができるでしょう。
任意後見制度の導入をご検討中の方は、お気軽に法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に法的サービスを提供しております。当事務所では、任意後見・遺言・死後事務委任等に関する初回相談を無料で承っております。認知症対策、相続対策、事業承継対策など、あなたの悩みに合わせた最適なプランをご提案いたします。「任意後見」についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
早めの準備がトラブルを防ぎます。あなたの大切な生活を守るための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
併せて読みたいオススメ記事