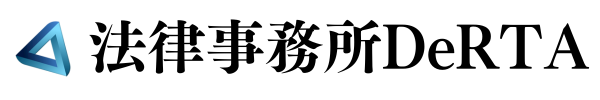任意後見人を2人以上にすることはできる?複数受任者の選任の可否と方法を解説

「将来、認知症などで判断能力が衰えてしまったら、財産管理や介護の手続きはどうしよう…」そんな不安に備えるための制度が「任意後見契約」です。信頼できる人に将来の支援を託すこの制度ですが、「頼みたい人が一人ではない」「一人に任せるのは負担が大きいかもしれない」と考える方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、任意後見契約において受任者(任意後見人になる人)を複数選任できるのか、また、その場合にどのような方法があるのかを、具体的な活用場面や注意点とあわせて詳しく解説します。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見受任者)に、財産の管理や介護・医療の手続きなどの事務を委任する契約です。
この契約は、公証役場で公正証書によって結ぶ必要があり、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、その効力が生じます。
任意後見契約を必要とする背景
現代の日本では、高齢化が急速に進み、認知症患者数も増加の一途をたどっています。判断能力が低下すると、ご自身で預貯金の引き出しや不動産の管理、介護サービスの契約などが困難になる可能性があります。このような事態に備え、ご自身の意思に基づいた将来設計を可能にする任意後見制度の重要性が高まっています。
任意後見契約の具体的な活用場面【3つのケース】
具体例1:日々の財産管理に不安があるケース
最近物忘れが増え、公共料金の支払いや預金の引き出しが不安になってきた高齢者が、あらかじめ子を受任者とする契約を結びます。将来、判断能力が低下した際には、子が代理人として以下の手続きを合法的に行えるようになります。
- 預貯金の管理や生活費の払い戻し
- 家賃や公共料金、税金の支払い
- 不要な契約をしてしまった場合の取消し手続き
具体例2:将来の不動産売却に備えたいケース
将来、介護施設に入る資金として自宅の売却を考えている方が、判断能力の低下で売買契約ができなくなる事態に備え、信頼できる親族や専門家を受任者として契約します。これにより、本人の意思に基づき、最適なタイミングで代理人が以下の手続きを進められます。
- 不動産会社との媒介契約
- 買主との売買契約の締結と代金の受領
- 施設入居金などへの充当
具体例3:身近に頼れる親族がいないケース
身寄りのない方が、もしもの入院や介護が必要になった場合に備え、信頼する友人を受任者とする契約を結びます。財産管理だけでなく、生活に関する手続き(身上監護)も任せられます。代理人は本人の希望に沿って、以下の手続きを行えます。
- 本人の希望(療養環境など)を医療・介護関係者に伝える
- 病院の入退院手続きや、介護保険の申請
- 介護サービスの利用契約
任意後見契約において受任者を複数にできるのか?
任意後見契約において、受任者が複数いれば、より安心して後見事務を任せられることも考えられます。このようなことはできるのでしょうか?
複数選任の可否
結論から言いますと、任意後見契約の受任者を複数にすることは可能です。
任意後見契約は、民法上の「委任契約」の一種です。委任契約では、誰に何を委任するかを当事者が自由に決めることができる「契約自由の原則」が働くため、受任者を複数人にすることも認められています。ただし、後述するように、複数にする場合には権限の行使方法などを明確に定めておく必要があり、注意が必要です。
複数選任の種類
受任者を複数にする場合、以下の3つの方法が考えられます。契約を結ぶ際には、どの方法がご自身の希望に最も合っているかを慎重に検討する必要があります。
- 各自代理方式
- 共同代理方式
- 予備的受任者の設定(各自代理方式において)
次章から、それぞれの方式について詳しく見ていきましょう。
任意後見契約における複数の受任予定者の各自代理方式について
各自代理方式とは?それぞれが単独で代理できる形式
各自代理方式とは、選任された複数の受任者が、それぞれ単独で代理権を行使できる形式です。例えば、受任者が長男と長女の2人いる場合、長男だけで、あるいは長女だけで、契約で定められた手続き(預貯金の払い戻しや介護契約など)を行うことができます。
契約締結の方法として、同時に1通の公正証書で行うこともできますし、異なる時期に別個に公正証書を作成することで行うこともできます。
活用場面
各自代理方式は、その柔軟性から様々なケースで活用が検討されます。
- 受任者が離れた地域に住んでいる場合
- 例:実家の近くに住む長女と、遠方に住む長男を受任者にするケース。普段の生活費の管理や細かな手続きは長女が行い、不動産の売却など重要な手続きの際には長男も関与するなど、役割分担がしやすくなります。
- 専門家と親族を組み合わせる場合
- 例:財産管理に詳しい弁護士等の専門家と、本人の生活状況をよく知る親族を受任者にするケース。専門的な知識と身上監護の視点を両立させ、より手厚いサポートが期待できます。
- 受任者の負担を軽減したい場合
- 複数の受任者がいれば、一人当たりの負担が軽減され、継続的なサポートが可能になります。
メリットと注意点
任意後見契約において各自代理方式の複数の受任者を選任するメリットとしては、上記のような役割分担のほか、1人の受任者に問題があっても他方の受任者が任意後見人として活動できる点です。
他方で、複数受任者はそれぞれ代理権を有するので、役割分担をはっきりさせないと混乱や権限の濫用が発生する可能性があり、注意が必要です。なお、受任予定者を複数選任する場合、公正証書の作成手数料や印紙代等も複数分必要となります。
任意後見契約における複数の受任予定者の共同代理方式について
共同代理方式とは?二人以上の同意が必要な形式
共同代理方式とは、選任された複数の受任者が、共同でなければ代理権を行使できない形式です。「全員の同意」を必要とするのが一般的ですが、「過半数の同意」など、契約で別段の定めをすることも可能です。
この方式を採用する場合、契約書(公正証書)にその旨を明確に記載する必要があります。
共同代理方式の活用場面
- 財産額が大きく、慎重な管理が求められる場合
- 高額な財産を動かす際に、複数の目によるチェック機能が働くため、不正防止や慎重な判断につながります。
- 受任者間の相互監視を機能させたい場合
- 受任者同士で牽制し合うことで、一人の独断による不適切な財産処分などを防ぐ効果が期待できます。
共同代理方式のデメリット・注意点
共同代理方式には、慎重な判断ができるというメリットがある一方、以下のようなデメリットも存在します。
- 手続きの遅延リスク
- すべての手続きに全員の同意が必要なため、意思決定に時間がかかり、機動性に欠ける可能性があります。緊急の支払いなどに対応しにくい場面も想定されます。
- 意見対立による停滞リスク
- 受任者間で意見が対立してしまうと、何も決められなくなり、後見事務そのものが停滞してしまう恐れがあります。
- 契約の不可分性
- 共同代理方式における複数受任者の各任意後見契約は不可分とされています。したがって、複数受任者の1人に不適任事由がある場合には任意後見人の選任ができず、また複数受任者の任意後見人の選任後に1人に終了事由(契約解除等)が発生した場合、全体の任意後見契約が失効してしまいます。
以上のように、意見対立や契約の失効の問題があるので、共同代理方式は特別な理由がない限りお勧めできません。
任意後見における予備的受任者の設定とは?

予備的受任の必要性:主たる受任者が対応できない場合の備え
受任者として信頼する人を選んでも、その人がご自身より先に亡くなったり、病気や高齢で後見事務を行えなくなったりする可能性はゼロではありません。主たる受任者が対応できなくなった場合、任意後見契約はその時点で終了してしまい、改めて法定後見の申し立てが必要になることもあります。
このような事態に備え、「主たる受任者が任務を行えなくなった場合に、その任務を引き継ぐ人」を予備的受任者として定めておくことが考えられます。
予備的受任の登記の可否
現在の法律(後見登記等に関する法律)では、「AさんがダメになったらBさん」というような順位を付けた形での登記は認められていません(後見登記法5条参照)。登記上は、主たる受任者も予備的受任者も、同順位の「任意後見受任者」として登記されます。
予備的受任を実現する方法
登記制度上は順位付けができませんが、契約内容の工夫によって、実質的に予備的受任を実現することが可能です。
具体的には、1通の公正証書の中で、主たる受任者と予備的受任者のそれぞれと各自代理方式での任意後見契約を結びます。そして、予備的受任者との契約部分に「主たる受任者の死亡、辞任、解任、その他後見事務の遂行が困難となった場合に限り、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行う」といった趣旨の特約を設けます。
この特約は家庭裁判所を直接拘束するものではありませんが、当事者間の合意として有効であり、実務上も広く用いられている方法です。
条項例
以下は、予備的受任を定める場合の契約条項の一例です。
第●条(契約の趣旨)
甲は、乙及び丙に対し、令和●年●月●日、任意後見契約に関する法律に基づき、甲が精神上の障害により、判断能力が不十分になった場合に、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことを委任し、乙及び丙はこれを受任する(以下「本契約」という。)。
第●条(契約の発効)
1 本契約のうち甲乙間の契約は、甲が精神上の障害により判断能力が不十分になった場合において、乙が家庭裁判所に対し、乙について任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本契約のうち甲丙間の契約は、前項の場合において乙が速やかに前項の請求をしないとき、又は乙の死亡若しくは病気等により乙の任意後見人としての職務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合に、丙が家庭裁判所に対し、丙について任意後見人の選任を請求し、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
複数受任者を設定する際の注意点と実務上のポイント
適切な設計の必要性:意思決定の分散による混乱リスク
受任者を複数にすると、安心感が増す一方で、意思決定のプロセスが複雑になり、かえって混乱を招くリスクもあります。誰が、いつ、どのような権限を行使するのか、受任者間の報告・連絡・相談のルールはどうするのかなど、具体的な運用方法まで見据えた上で、契約内容を設計することが極めて重要です。
契約書への明確な規定の重要性
「各自代理」にするのか「共同代理」にするのかは、任意後見契約の根幹をなす重要な事項です。この点を公正証書に明確に規定しておかなければ、後々、受任者間や親族間でのトラブルに発展しかねません。また、特定の事務についてのみ共同代理とするといった、柔軟な設計も可能です。
弁護士等の専門家への相談の必要性
ご自身の希望や家族の状況に最適な契約内容を設計するためには、法的な知識と実務経験が不可欠です。任意後見に詳しい弁護士などの専門家に相談し、想定されるリスクやその対策について十分に検討した上で、契約内容を固めていくことを強くお勧めします。
まとめ:任意後見における複数受任者の活用と留意点
複数受任者の活用と留意点まとめ
- 複数選任は可能:任意後見の受任者は、複数人選ぶことができます。
- 方式は主に3種類:
- 各自代理:迅速・柔軟な対応が可能。役割分担がしやすい。
- 共同代理:慎重な判断が可能で、不正防止に繋がるが、手続きが遅れるリスクも。
- 予備的受任:主たる受任者の「もしも」に備えるための有効な手段。
- 契約内容の明確化が必須:権限の範囲や行使方法を公正証書に明確に定めることがトラブル防止の鍵です。
弁護士に相談して安心・確実な契約を
任意後見契約は、ご自身の人生の終盤を支える、非常に重要な契約です。複数の受任者を立てる場合は、その設計がより複雑になります。
任意後見契約の設計でお悩みの方は、ぜひ法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。
当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に法的サービスを提供しています。
複数受任者の活用や、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約との組み合わせなど、将来の不安を解消するためのオーダーメイドの提案が可能です。初回相談は無料で承っております。
任意後見についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
併せて読みたいオススメ記事