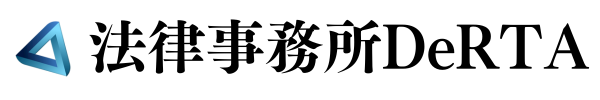任意後見契約の解除|家庭裁判所の許可は必要?選任前・後の手続きと登記申請をステップで解説

「将来のために任意後見契約を結んだけれど、状況が変わったので解除したい」「任意後見人をお願いした相手と信頼関係が崩れてしまった」など、一度結んだ任意後見契約の解除についてお悩みではありませんか。
任意後見契約は、ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、将来の代理人(任意後見人)を自ら選んでおくための大切な制度です。しかし、様々な事情で契約を見直したいと考えることもあるでしょう。
この記事では、任意後見契約を解除するための具体的な手続きを、状況別にステップで解説します。「家庭裁判所の許可は必要なのか」「どんな書類がいるのか」といった疑問にもお答えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「任意後見制度」とは?
任意後見契約の解除について知る前に、まずは「任意後見制度」そのものの基本的な仕組みを理解しておきましょう。
判断能力があるうちに将来の備えをする制度
任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、元気なうちに「誰に(任意後見人)」「どのような支援を(代理権の範囲)」してもらうかを、自らの意思で決めておく制度です。
判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」とは異なり、自分の信頼する人を後見人に選べるのが最大の特徴です。
任意後見契約と公正証書
任意後見契約は、口約束や当事者間だけで作成した契約書では効力が認められません。法律により、必ず公証役場で「公正証書」を作成する必要があります。公証人が契約内容の適法性や本人の意思を確認するため、契約の信頼性と安全性が確保されています。
契約の開始と「任意後見監督人」の役割
契約を公正証書で結んだだけでは、すぐに後見がスタートするわけではありません。
実際に本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に対して**「任意後見監督人」**の選任申立てを行います。そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点ではじめて契約の効力が生じ、任意後見人が活動を開始できます。
この「任意後見監督人」が選任されているかどうかが、本記事のテーマである「契約解除」の手続きを左右する極めて重要なポイントとなります。
任意後見契約の解除とは
このような仕組みの任意後見契約ですが、一度結んだら絶対に解消できないというものではありません。法律で定められた手続きを踏むことで、契約の効力を将来に向かって失わせる、つまり解除することが可能です。
任意後見契約解除の基本的な仕組み
任意後見契約は、一度結んでも、特定の条件下で終了させることができる、という基本原則があります。ただし、誰が、いつ、どのような理由で解除するかによって、その方法は大きく異なります。特に重要なのが、前述した「任意後見監督人」が選任されているかどうかです。
解除できるタイミングと制限
任意後見契約を解除する上で最も重要な分岐点は、「任意後見監督人が選任される前か、後か」というタイミングです。
- 選任前:まだ契約の効力が発生していない段階。比較的自由に解除が可能ですが、法律で定められた厳格な方式が求められます。
- 選任後:すでに契約の効力が発生し、後見が開始されている段階。本人の保護が優先されるため、解除には一定の制限が課せられます。
ご自身の状況がどちらに当てはまるのかを、まず正確に把握することが重要です。
任意後見監督人選任前の解除方法
解除の可否及び手続
任意後見監督人が選任される前(=本人の判断能力が低下する前)であれば、当事者の意思に基づいて契約を解除することができますが、公証人の認証等の一定の手続が必要です。なお、契約を解除したあとは、後述のとおり登記手続が必要となります。
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)
(任意後見契約の解除)
第九条 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
当事者双方の合意による解除
最も円満な方法は、本人と任意後見受任者(後見人になる予定の人)の双方が合意の上で解除する「合意解除」です。双方の合意があるので、問題なく解除は有効です。この場合、「任意後見契約合意解除契約書」などの書面を作成し、その書面について公証人の認証を受ける必要があります。
一方的な解除が可能な場合とその方法
任意後見契約の効力が発生する前であれば、本人または任意後見受任者のどちらからでも、理由を問わず一方的に契約を解除することができます。ただし、この場合も単に通知するだけでは足りず、解除の意思表示を記載した書面について公証人の認証を受け、それを相手方に送付する手続きが必要です。
注意が必要なのは、任意後見契約の契約書に「委任者は、正当な事由がある場合に限り、任意後見契約を解除できる」という定めがある場合です。この合意について、委任者側の解除を制限することは公序良俗に違反するという見解もあるところですが、任意後見法9条1項は立法担当者によれば強行規定ではないとのことなので、有効とせざるを得ないように思います。この場合でも、「正当な事由」を比較的緩やかに解釈することによって対処することが可能なのではないでしょうか。まだ問題となった事例はないようですが、裁判所の判断が待たれるところです。
解除の通知とその形式(公証人の認証の必要性)
上記のとおり、任意後見監督人が選任される前の解除では、「公証人の認証を受けた書面」を用いることが法律で定められています。
これは、重要な契約である任意後見契約が安易に解除されることを防ぎ、当事者の真摯な意思を確認するための手続きです。公証人が当事者の本人確認を行い、本人の意思に基づいて書面が作成されたことを公的に証明します。
口頭での約束や、当事者間だけで作成した書面に署名・押印しただけでは、法律上の解除の効力は生じません。一方的な解除の場合において、認証を受けた書面を相手方に送付する際には、送達を証明できる「内容証明郵便(配達証明付)」で送付することが必要ですので、ご注意ください。
任意後見監督人選任後の解除方法と制限
任意後見監督人が選任された後は、すでに後見が開始されています。この段階では、本人の保護が最優先されるため、当事者の都合だけで契約を解除することはできません。
家庭裁判所による解除の必要性
監督人選任後は、当事者間の合意や一方的な通知だけでは契約を解除できません。必ず家庭裁判所の許可が必要になります。これは、本人の利益を損なう不当な解除を防ぎ、後見制度の公的な役割を担保するためです。
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)
(任意後見契約の解除)
第九条 (略)
2 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
解除が認められる事由(受任者の不正行為・能力不足など)
家庭裁判所が解除を許可するには「正当な事由」が必要です。その内容については明記されておりませんが、具体的には以下の場合が考えられます。
- 財産の使い込みや不適切な管理(不正行為)
- 本人への虐待や暴言(著しい不行跡)
- 病気や破産など、後見事務を継続できない状況(任務に適しない事由)
- 本人との信頼関係が完全に破綻し、協力して財産管理ができない状況
単に「相性が悪い」といった主観的な理由だけでは、正当な事由として認められるのは難しいでしょう。
申立てから解除決定までの流れ
- 申立て:本人、親族、検察官などが、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見契約解除の許可」を申し立てます。
- 審理:家庭裁判所は、申立人や任意後見人から事情を聴いたり、必要な調査を行ったりします。
- 審判(決定):審理の結果、正当な事由があると認められれば、家庭裁判所は解除を許可する審判を下します。

任意後見契約の解除登記の手続き
契約解除の手続きが完了したら、最後に法務局でその旨を登記する必要があります。これは、監督人選任の前後にかかわらず、すべての解除ケースで必須の手続きです。
登記申請の必要性と法的根拠
任意後見契約は公的に登記されており、その内容は誰でも確認できます。そのため、契約を解除した事実も登記簿に反映させなければ、第三者から見ると契約が続いているように見えてしまいます。
この「終了の登記」を怠ると、例えば、すでに解除された元任意後見人が、その立場を悪用して第三者と取引をしてしまうなどのリスクが生じます。登記をすることで、契約が終了したことを公的に証明し、こうしたトラブルを防ぐことができます。
解除登記に必要な書類(契約書、裁判所決定書など)
登記申請には、解除の事実を証明する書類が必要です。
- 監督人選任前の解除の場合:公証人の認証を受けた「合意解除証書」や「解除通知書」(内容証明・配達証明書)
- 監督人選任後の解除の場合:家庭裁判所が発行する「審判書謄本」と「確定証明書」
この他に、登記申請書、当事者の本人確認書類や住民票などが必要となる場合があります。
登記申請の流れと所要期間
申請は、東京法務局の後見登録課に対して行います(書留郵便等による郵送も可)。書類に不備がなければ、申請から1〜2週間程度で登記が完了します。登記手数料は無料です。
任意後見契約解除のまとめと相談のすすめ
最後に、任意後見契約を解除する上で押さえておくべきポイントと、専門家への相談について解説します。
解除にあたって注意すべきポイント
- タイミングの確認:まずは「任意後見監督人」が選任されているかを確認しましょう。手続きが全く異なります。
- 厳格な方式の遵守:特に監督人選任前は、「公証人の認証を受けた書面」が必須です。この形式を欠くと解除は無効となります。
- 終了登記の実行:契約解除と登記はワンセットです。登記完了まで確実に行いましょう。
専門家に依頼するメリット
任意後見契約の解除は、法律で定められた厳格な手続きが求められます。特に、公証役場での認証手続きや家庭裁判所への申立ては、専門的な知識がないと難しい場面も少なくありません。
弁護士などの専門家に依頼すれば、
- ご自身の状況に合った最適な解除方法を提案してもらえる
- 相手方との交渉や法的に有効な書類作成を任せられる
- 公証役場、家庭裁判所、法務局での複雑な手続きを代行してもらえる
といったメリットがあり、スムーズかつ確実に問題を解決に導くことができます。手続きに不安を感じたら、まずは一度専門家に相談してみることをお勧めします。
ご相談は法律事務所DeRTAへ
任意後見制度の後見人候補者その他をご検討中の方は、お気軽に法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に法的サービスを提供しております。
当事務所では、任意後見・遺言・死後事務委任等に関する初回相談を無料で承っております。認知症対策、相続対策など、あなたの悩みに合わせた最適なプランをご提案いたします。「任意後見」についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
早めの準備がトラブルを防ぎます。あなたの大切な生活を守るための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
併せて読みたいオススメ記事