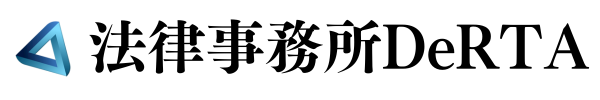任意後見制度の理解を深める – 事理弁識能力・意思能力とは

任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、ご自身の判断能力が認知症や病気などによって不十分になった場合に備えて、判断能力があるときに、あらかじめ支援をお願いしたい人(任意後見人)と、その方にどのような支援(財産管理や身上監護)をしてもらうかを、ご自身で決めておく制度です。
法定後見制度が、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選ぶのに対し、任意後見制度はご本人の意思を最大限に尊重し、「誰に」「何を」お願いするかを事前に決めておけるのが大きな特徴です。まさに、ご自身の未来をご自身の意思でデザインするための制度といえます。
「意思能力」とは
意思能力の内容・法的根拠・具体例
意思能力とは、ご自身の行った行為がどのような法的な結果をもたらすのかを、正しく理解・判断できる精神能力のことを指します。法律行為が有効に成立するための、最も基本的な前提条件です。
この意思能力については、2020年4月1日に施行された改正民法で、その効果が明確に条文に定められました。
民法 第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
しかしながら、要件である「意思能力」の定義は設けられてないため、解釈に委ねられることになります。基本的には、意思能力の有無は、当事者が行った法律行為の性質や難易等を考慮して個別具体的に判断されることになります(東京地判平成17年9月29日判タ1203号173頁等)。
【具体例】
例えば、以下のような方が行った契約は、意思能力がなかったものとして無効になる可能性があります。
- まだ物事の判断ができない幼児
- お酒に酔って正常な判断ができない泥酔者
- 重度の認知症や精神障害により、契約内容を全く理解できない方
任意後見契約における意思能力の必要性
任意後見契約も、法律上の「契約」の一種です。したがって、契約を締結するご本人に意思能力がなければ、その契約は無効となります。たとえ公正証書という厳格な形式で作成したとしても、契約時にご本人の意思能力が欠けていたと判断されれば、契約そのものが成立していなかったことになってしまいます。
そのため、公証人は契約作成の際、ご本人と面談し、契約内容を理解しているか、ご自身の意思で契約しようとしているかなどを慎重に確認します。
意思能力は個別具体的に判断されるべきところ、任意後見契約において、どのような内容の意思能力が必要かを巡って、様々な見解が存在するところです。たとえば、誰を任意後見契約の受任者とするか、どのような法律行為について代理権を付与するのかを理解しているかどうかを必要とする見解や、報酬を支払う場合には委託内容に見合った報酬額を判断し決定する精神能力まで必要とする説などがあります。
「事理弁識能力」とは
事理弁識能力の内容
事理弁識能力とは、物事の道理や善悪、結果をわきまえて判断する能力を指します。つまり判断能力のことです。意思能力が「あるか・ないか」のゼロか百かで語られることが多いのに対し、事理弁識能力は「どの程度あるか」というレベル(程度)で評価される能力です。
法定後見制度(後見・保佐・補助)は、この事理弁識能力の程度によって、以下のように類型が分かれています。
- 後見:事理弁識能力を欠く常況にある方
- 保佐:事理弁識能力が著しく不十分な方
- 補助:事理弁識能力が不十分な方
任意後見において事理弁識能力はどのような意味を持つか
事理弁識能力は、任意後見制度において「契約の発効時(スタート時)」の場面で重要な意味を持ちます。
すなわち、締結した任意後見契約は、すぐに効力が生じるわけではなく、将来、ご本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から効力が生じます。この「判断能力が低下した段階」とは、法律上「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」と定められており(任意後見契約に関する法律第4条)、まさに事理弁識能力の低下が、任意後見をスタートさせるためのスイッチとなるのです。
任意後見契約に関する法律
(任意後見監督人の選任)
第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。(以下略)
被保佐人・被補助人相当の者による任意後見契約締結の可否
それでは、事理弁識能力が「著しく不十分」または「不十分」であることが要件とされ被保佐人・被補助人に相当する方は、任意後見契約を締結できるのでしょうか。
法律上、被保佐人・被補助人相当であることをもって、直ちに任意後見契約を結べなくなるわけではありません。上記のとおり、任意後見契約を締結できるだけの意思能力があると認められれば、被保佐人・被補助人相当の者も任意後見契約を締結することが可能です。ただし、契約締結に必要な意思能力が備わっているかについて、より慎重な判断が求められます。
この場合、いわゆる任意後見契約の類型のうち、「即効型」で契約を締結することになると思いますが、即効型の利用は慎重に検討すべきとする見解も存在するところです(下記記事参照)。

実務上は、公証人が本人の状態を審査することもあり、医師による専門的な診断書の提出を求められることもあります。そして、本人の状態によっては、契約締結が難しいと判断されるケースもあります。この場合には、任意後見契約ではなく、保佐や補助の審判の申立てをせざるを得ません。

任意後見契約において意思能力の有無が争点となった裁判例(福岡家庭裁判所 審判 平成28年10月27日・判例時報2372号51頁)の紹介
契約締結時に本人の意思能力があったかどうか、どのように問題になるかを理解するために、1つ裁判例を紹介します。
【福岡家庭裁判所 審判 平成28年10月27日】(判例時報2372号51頁)
事案の概要
本人が、長女Aさんとの任意後見契約を解除し、同日に長男Bさんとの間で新たな任意後見契約を締結しました。しかし、この契約変更の時点で、本人は既にアルツハイマー型認知症と診断されており、短期記憶の低下が著しい状態でした。そのため、契約変更の効力(本人の意思能力の有無)が裁判で争われました。
裁判所の判断(意思能力について)
裁判所は、本人の意思能力について様々な事実から検討しました。
- 契約変更以前から、医師により高度アルツハイマー型認知症と診断され
- 短期記憶の低下が著しく、買い物や服薬の管理も困難な状況であったこと。
- ある親族と対立していたにもかかわらず、急にその親族と再開して平然と自宅で生活するなど、短期記憶に問題があったこと
これらの状況から、本人の意思能力は相当程度低下していたと指摘しました。一方で、
- ある医師が本人の見当識はほぼ保たれ、意思疎通も問題なく、脳の萎縮又は損傷は年齢相応に部分的に見られるとしていること、会話は流暢であり、社会性は保たれ流通性も良好で、場所の見当識は保たれ、計算はある程度は可能などとしていること
- 記銘力は重度に低下しているものの、意識は清明で、質問の意味を理解し、概ね適切に答え、見当識は、場所、人物について保たれ、理解力・判断力については、後見人の意味を大まかに理解し、財産についても不動産については認識していること
といった点も認められるとしました。
結論裁判所は、これらのプラス・マイナス両面の事実を総合的に評価した結果、「本人の意思能力が完全に失われる程度にまで低下していたと認めることは困難」と判断しました。
最終的に、従前の任意後見契約の解除と新たな任意後見契約の締結自体は意思能力の欠如を理由に無効とは断定できない、と結論付けました(※なお、この裁判例では、契約は無効ではないとしつつも、他の事情から任意後見契約を発効させるのは相当ではないとして、法定後見を開始する決定がなされています)。
なお、この審判の中では、「任意後見契約締結の際に、本人に意思能力の低下が認められる場合、本人が代理権の個別具体的な内容を全て理解することまでは必要ではなく、受任者が本人に関する包括的な権限を獲得し、本人自身がしたであろう一切の事項を本人の財産についてすることができ、本人が意思無能力となっても権限は継続することさえ理解することができれば契約は有効というべきである。」とも述べられています。
まとめ
任意後見制度は、ご自身の意思で将来に備えるための非常に有効な手段です。しかし、その大前提として、契約時にご本人に十分な意思能力が備わっている必要があります。
判断能力が低下してからでは、この制度を利用することはできないこともあり得ます。また、能力の有無が曖昧な状態で契約を結ぶと、後々、契約の有効性をめぐって親族間の紛争に発展するおそれもあります。
ご自身の将来のために任意後見制度の利用を検討される際は、判断能力がしっかりしているうちに、お元気な段階から準備を始めることが何よりも大切です。少しでも不安な点があれば、弁護士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。
弁護士に相談して安心・確実な契約を
任意後見契約の設計でお悩みの方は、ぜひ法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。
当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に法的サービスを提供しています。
複数受任者の活用や、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約との組み合わせなど、将来の不安を解消するためのオーダーメイドの提案が可能です。初回相談は無料で承っております。
任意後見についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
併せて読みたいオススメ記事