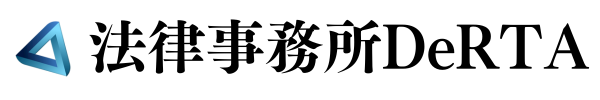遺言の種類とは?自筆証書・公正証書・秘密証書遺言の違いとメリット・デメリット

「自分の財産は、自分の意思で、大切な人に確実に遺したい。」 「残された家族が相続で揉めることのないようにしたい。」このように、ご自身の将来やご家族のために遺言の作成を考える方が増えています。しかし、遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットが存在することをご存知でしょうか。
遺言は、法律で定められた形式を守らなければ無効になってしまう可能性があります。ご自身の想いを法的に有効な形で実現するためには、遺言の種類を正しく理解し、ご自身の状況に最も適した方式を選ぶことが非常に重要です。
この記事では、遺言の主な3つの種類「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について、弁護士がそれぞれの特徴とメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
遺言の種類は大きく3つに分けられる
法律(民法)で定められている遺言の方式には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」があります。特別方式は、病気や災害などで死期が迫っているなど、特殊な状況下で認められる例外的なものです。
一般的に遺言を作成する場合は「普通方式」を用います。そして、この普通方式には以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
- 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
- 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
この3つの方式は、作成方法、費用、効力の確実性などが大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合ったものを選ぶことが、円満な相続の第一歩となります。
自筆証書遺言の特徴とメリット・デメリット
特徴
自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成する遺言です。証人は不要で、最も手軽に作成できる方式です。
2019年の法改正により、財産の内容を記載した「財産目録」については、パソコンでの作成や、通帳のコピー・不動産の登記事項証明書などを添付することが認められるようになりました(ただし、その目録の全ページに署名・押印が必要です)。
また、2020年からは法務局で自筆証書遺言を保管してくれる「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、紛失や改ざんのリスクを減らせるようになりました。
メリット
- 手軽で費用がかからない:紙とペン、印鑑さえあれば、思い立った時にいつでも作成でき、費用もほとんどかかりません。
- 内容を秘密にできる:誰にも知られることなく、自分一人で遺言の内容を決めて作成することができます。
デメリット
- 形式不備で無効になるリスクが高い:全文自書、日付、氏名、押印など、法律で定められた形式を一つでも欠くと遺言全体が無効になってしまう危険性があります。
- 紛失・隠匿・改ざんのリスク:自宅などで保管する場合、紛失したり、相続人に発見されなかったり、あるいは一部の相続人によって隠されたり改ざんされたりする恐れがあります。(※法務局の保管制度を利用することで、このリスクは回避できます)
- 家庭裁判所の「検認」が必要:遺言者の死後、相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」という手続きを経る必要があります。これには時間と手間がかかります。(※法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要です)
- 内容が不明確でトラブルになる可能性:法律の専門家が関与しないため、表現が曖昧であったり、法的に実現不可能な内容であったりして、かえって相続人間の紛争の火種となることがあります。
公正証書遺言の特徴とメリット・デメリット
特徴
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、2人以上の証人の立会いのもとで、遺言の内容を公証人に伝え、その内容を公証人が法律に則って文書にまとめることで作成する遺言です。作成された遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。
メリット
- 極めて無効になりにくい:法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式の不備で無効になる心配はまずありません。
- 紛失・改ざんのリスクがない:原本が公証役場に保管されるため、紛失、盗難、隠匿、改ざんの恐れがありません。
- 家庭裁判所の「検認」が不要:遺言者の死後、検認手続きを経ずに、速やかに相続手続きを開始することができます。
- 証明力が高く、紛争を予防できる:公証人が遺言者の意思能力や本人確認をしっかり行うため、後になって「本人が書いたものではない」「判断能力がない状態で書かされた」といった争いが生じにくいです。
デメリット
- 費用がかかる:公証人に支払う手数料が必要です。手数料は、相続させる財産の価額によって変動します。たとえば、遺言の目的物の価額が5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円の手数料がかかります。
- 手間と時間がかかる:公証人との事前打ち合わせや、必要書類の収集など、作成にある程度の準備と時間が必要です。
- 証人が2人以上必要:証人には、遺言の内容が知られることになります。適当な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です(別途費用がかかります)。
- 内容の秘密を確保できない:公証人のほかに証人2人に遺言の内容を明らかにしなければならないため、内容の秘密を確実に確保することはできません。
秘密証書遺言の特徴とメリット・デメリット
特徴
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま遺言書を封じ、その存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。 遺言者本人が作成した遺言書(パソコン作成や代筆も可。ただし署名は自書)に署名・押印し、封筒に入れて封印します。その封書を公証人と2人以上の証人の前に提出し、自分の遺言書であることを申述します。
メリット
- 内容を秘密にできる:公証人や証人にも、遺言の中身を知られることはありません。
- 遺言の存在が公的に証明される:公証役場で手続きを行うため、遺言書が存在すること、そしてそれが本人のものであることが明確になります。
- 偽造・変造のリスクが低い:封印された状態で公証役場に記録が残るため、偽造や変造を防ぐ効果があります。
デメリット
- 内容の不備で無効になるリスク:自筆証書遺言と同様に、遺言の内容自体は公証人がチェックしないため、法律的な不備によって無効となる可能性があります。
- 費用と手間がかかる:公証人手数料や証人が必要となり、自筆証書遺言より手間も費用もかかります。
- 家庭裁判所の「検認」が必要:自筆証書遺言(自宅保管の場合)と同様に、死後に家庭裁判所の検認手続きが必要です。
- 利用件数が少ない:手続きが煩雑である割に、内容の有効性が担保されないため、実際にはあまり利用されていないのが現状です。

遺言の種類を選ぶときの注意点と選び方
どの遺言方式が最適かは、その方の財産状況、家族関係、そして何を最も重視するかによって異なります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 手軽さ・費用 | ◎(最も手軽で安価) | △(費用・手間がかかる) | △(費用・手間がかかる) |
| 内容の秘密保持 | ◎(誰にも知られない) | △(証人・公証人は知る) | ◎(誰にも知られない) |
| 無効になるリスク | 高い | 極めて低い | 高い |
| 紛失・改ざんリスク | 高い(※) | ない | 低い |
| 検認手続き | 必要(※) | 不要 | 必要 |
(※)法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、紛失・改ざんリスクがなくなり、検認も不要になります。
【こんな方におすすめ】
- 自筆証書遺言:
- 費用をかけずに、まずは手軽に作成したい方。
- 財産構成がシンプルで、相続人間の関係も良好な方。
- (※作成する際は、紛争予防と手続きの簡略化のため法務局の保管制度の利用を強く推奨します。)
- 公正証書遺言:
- 最も確実で安全な方法を望むすべての方におすすめです。
- 相続財産が高額・複雑な方。
- 相続人間の関係が複雑で、将来争いになる可能性がある方。
- ご自身の死後、相続人に負担をかけたくない方。
- 秘密証書遺言:
- 遺言の内容は絶対に秘密にしたいが、その存在だけは公的に証明しておきたい方。
- (※ただし、内容の不備リスクを避けるため、作成前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。)
遺言の種類を正しく選ぶために専門家に相談する意義
ここまで3種類の遺言について解説してきましたが、「自分にはどれが合っているのか分からない」「自分で作った遺言が有効か不安」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
遺言は、あなたの最後の意思表示であると同時に、残されたご家族へのメッセージでもあります。その大切な想いを確実に実現し、「相続」が「争続」になってしまう事態を避けるためにも、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただくことで、以下のようなサポートが可能になります。
- 最適な遺言方式のご提案:ご自身の財産状況、ご家族への想い、将来の懸念などを丁寧にお伺いし、法的な観点から最も適した遺言の方式をアドバイスします。
- 法的に有効な遺言内容の作成:ご希望に沿いながら、遺留分など将来の紛争リスクを考慮した、法的に有効で争いのない遺言書の作成をサポートします。
- 各種手続きの支援:公正証書遺言を作成する際の公証人との打ち合わせや証人の手配、自筆証書遺言の法務局保管制度の申請手続きなどもお手伝いします。
- 遺言執行者への就任:遺言の内容を責任をもって実現する「遺言執行者」に弁護士が就任することで、ご自身の死後、相続手続きが円滑かつ正確に進むよう万全を期すことができます。
遺言書の作成は、決して後ろ向きな準備ではありません。ご自身が安心した人生を送り、大切なご家族が円満に未来へ進むための、前向きで愛情のこもった準備です。 まずはお気軽にご相談いただき、あなたの想いを形にするお手伝いができれば幸いです。
遺言でお悩みの方は、ぜひ法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。
当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に法的サービスを提供しています。
遺言のほかに、高齢者向けのメニューとしえ、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約との組み合わせなど、将来の不安を解消するためのオーダーメイドの提案が可能です。初回相談は無料で承っております。
さらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
併せて読みたいオススメ記事