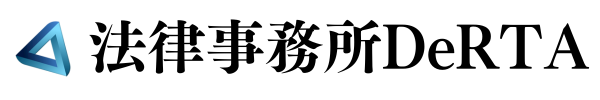任意後見人は株主の議決権行使ができる?法律上の位置付けと注意点

会社の経営者や大株主の方が、将来、ご自身の判断能力が低下してしまった場合、会社の重要な意思決定の場である株主総会で、誰が議決権を行使するのでしょうか。ご自身の意思を会社経営に反映させ続けるためには、事前の備えが不可欠です。
その備えの一つとして注目されているのが「任意後見制度」です。しかし、任意後見人が当然に株主の議決権を行使できるわけではありません。
本記事では、弁護士の視点から、任意後見人による株式会社の議決権行使の可否、その法律上の位置付け、そして実務上の注意点について詳しく解説します。
任意後見制度の概要
まずは、任意後見制度の基本的な仕組みについて理解しておきましょう。
任意後見契約の基本的仕組み
任意後見制度とは、ご本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ代理人(任意後見人)に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくものです。
この契約は、公証人が作成する公正証書によって結ぶことが法律で定められています。そして、ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その効力が生じます。
任意後見人の権限と役割
任意後見人の権限は、法定後見制度とは異なり、家庭裁判所が決定するのではなく、ご本人と任意後見人との間で締結した任意後見契約の内容によって決まります。
具体的には、契約書に添付される「代理権目録」に記載された法律行為を、ご本人に代わって行うことができます。逆に言えば、代理権目録に記載のない行為については、任意後見人として行うことはできません。
議決権行使とは?株主総会における重要性
次に、本記事のテーマである「議決権」について確認します。
議決権とは
議決権とは、株主が株主総会の決議に参加し、賛成または反対の意思表示をする権利のことです。株式会社の所有者である株主にとって、会社の経営に関する意思決定に参加するための最も重要かつ基本的な権利といえます。
議決権が問題となる場面
株主総会では、会社の根幹に関わる様々な重要事項が決議されます。
- 取締役や監査役の選任・解任
- 役員報酬の決定
- 定款の変更
- 合併、会社分割、事業譲渡などの組織再編
- 剰余金の配当
特に、中小企業のオーナー経営者様にとっては、ご自身やご親族が保有する株式の議決権は、会社の支配権そのものであり、その行方は会社の存続や事業承継に直結する極めて重要な問題です。
任意後見人による議決権行使の可否
それでは、本題である「任意後見人は議決権を行使できるのか」について、法定後見制度である成年後見人と比較しながら見ていきましょう。
成年後見人の場合
成年後見とは
成年後見制度は、既にご本人の判断能力が不十分になった後、親族等の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。本人の意思によらず、法律の規定に基づいて後見人が選任されるため「法定後見」とも呼ばれます。
成年後見人による株式会社の議決権の行使の可否
成年後見人の職務は、本人の財産を適切に管理し、保護すること(財産管理権)が基本です。その権限は、民法上、「財産の保存行為」または「財産の性質を変えない範囲での利用・改良行為」に限定されています。
そのため、会社の経営方針に大きな影響を与える議決権の行使ができるかどうかは、見解が分かれています。たとえば、経営判断に基づく決議は一般的な後見事務として課すべきではないとする見解、身上監護のための財産管理として有意であれば認めるべきとする見解、行使はできるが本人の意向と最善の利益の観点から適切に行使すべきとする見解、親族間で経営をめぐる争いがあるか否かによって検討し中立的立場を堅持するとする見解、議決権行使が従前の経緯等を考慮して後見人の裁量を逸脱するものでなく本人の意思に反するものとまではいえないかを判断すべきとする見解などがあるところです。
代理権目録に会社及び株式を指定して「本人が有する自社株の株主権の行使」と記載がある場合
任意後見契約において、議決権行使の権限を任意後見人に与えるための最も確実な方法です。
代理権目録に、「本人の有するA株式会社の株式に関する株主としての権利(議決権行使を含む)の一切の行使に関する事項」といった形で、対象となる会社や株式を特定し、議決権行使に関する権限を明確に記載しておくことで、任意後見人はその記載に基づいて、正当な代理人として議決権を行使することができます。
会社の経営権や事業承継をお考えの場合、このような具体的な記載は必須と言えるでしょう。
代理権目録に「不動産、動産等すべての財産の保全、管理及び処分に関する事項」としか記載がない場合
公証役場で用意されている任意後見契約の標準的な代理権目録には、このような包括的な記載がされていることが多くあります。しかし、この記載だけでは、議決権を問題なく行使できるとは限りません。
ただ、この場合でも「すべての財産」に株式が含まれると解する見解も存在します。しかしながら、当然に含まれるかについて法的な解釈の余地があり、会社側から「代理権の範囲が不明確である」として議決権の行使を認められなかったり、他の株主からその有効性を争われたりするリスクが残ります。
したがって、上記のとおり個別具体的に記載する方が望ましいです。
代理権目録に関連する記載がない場合
言うまでもなく、代理権目録に議決権行使に関する記載が一切ない場合、任意後見人は株主としての議決権を行使する権限を持ちません。
もし任意後見人に議決権行使の権限を与えたい場合には、必ず代理権目録に記載しましょう。

任意後見人による議決権行使の方法
代理権目録に適切な記載があり、任意後見人が議決権を行使する権限を持つ場合、任意後見人としてはどのように議決権を行使すべきでしょうか。
本人が具体的に意向を示しているときは、これに従うべきことは言うまでもありません。たとえば、ライフプラン等で本人の意向が示されていれば、これに従って行使することになります。
もし本人の意向が示されていなかった場合には問題となりますが、意思決定支援ガイドラインに従って行使すべき、などの見解が存在します。
任意後見と議決権行使のまとめ
会社の経営者や株主にとって、将来の判断能力の低下は、会社の経営権そのものを揺るがしかねない重大なリスクです。任意後見制度は、このリスクに備えるための有効な手段となり得ます。
- 任意後見人の権限は、任意後見契約の内容(代理権目録)で決まる。
- 包括的な財産管理権限の記載だけでは、議決権行使が認められないリスクがある。
- 議決権行使を任意後見人に委ねるには、代理権目録にその旨を具体的に明記することが不可欠。
- 議決権の更新に関しては、ライフプランノート等で意向を記載しておくのがよい。
ご自身の意思を、判断能力が低下した後も会社の経営に反映させ続けるために、そして円滑な事業承継を実現するために、ぜひ任意後見契約の活用をご検討ください。
任意後見や議決権について専門家に相談するメリット
弁護士に相談して安心・確実な契約を
任意後見契約は、ご自身の将来を託す非常に重要な契約です。特に、会社の議決権のように専門的な知識を要する事項を盛り込む場合は、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
弁護士にご相談いただくことで、
- ご本人様の意思や会社の状況を丁寧にヒアリングし、将来起こりうるリスクを想定した、最適な代理権目録を作成できる。
- 議決権行使に関する具体的な条項の文言について、法的に有効かつ明確な形でアドバイスを受けられる。
- 任意後見契約全体の作成から、公証役場での手続き、将来任意後見が開始した後の実務まで、一貫したサポートを受けられる。
といったメリットがあります。
任意後見契約の設計でお悩みの方は、ぜひ法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。
当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に法的サービスを提供しています。
複数受任者の活用や、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約との組み合わせなど、将来の不安を解消するためのオーダーメイドの提案が可能です。初回相談は無料で承っております。
任意後見についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
併せて読みたいオススメ記事