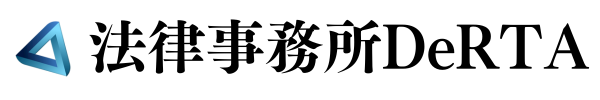2,000万円が消えた!?認知症高齢者の財産を守るには――見守り契約・財産管理契約・任意後見契約の重要性

「もし、あなたの親の預金通帳から、いつの間にか2,000万円もの大金が消えていたら…?」
にわかには信じがたい話かもしれませんが、これは特別なフィクションではなく、実際に起こった出来事です。認知症による判断能力の低下は、誰の親にも、そして将来的には自分自身にも起こりうる現実です。そして、その心の隙を狙って、虎視眈々と財産を搾取しようと待ち構えている人物が存在します。
大切な家族が人生をかけて築き上げてきた財産、そして穏やかであるべき老後の生活を守るために、私たちは何をすべきなのでしょうか。この記事では、認知症高齢者を狙う搾取の恐ろしい実態から、法的な予防策まで、弁護士が詳しく、そして深く解説します。
認知症高齢者を狙う搾取の実態
なぜ、認知症の高齢者がいとも簡単に狙われてしまうのでしょうか。そこには、病気の特性と、それを取り巻く社会的な背景が複雑に絡み合っています。
なぜ認知症の方が狙われやすいのか
認知症の中核的な症状は、記憶障害や判断能力の低下です。これにより、「高額な商品でも価値が分からず言われるがままに契約してしまう」「お金を支払ったことを忘れ、何度も請求に応じてしまう」といったことが起こります。また、複雑な契約書を読むのが億劫になり、「大丈夫だろう」と安易にサインしてしまうことも少なくありません。
さらに深刻なのは、心理的な脆弱さです。配偶者との死別や子供の独立による孤独感は、「自分は一人ではない」と思わせてくれる相手への強い依存心を生みます。その結果、「いつも親切にしてくれるあの人が、悪い人のはずがない」という正常性バイアスが働き、たとえ家族が警告しても、搾取されている本人だけが最後まで加害者を信じ続けてしまうという悲劇が起こるのです。
身近に潜む加害者――業者や知人による搾取
財産を搾取するのは、いかにも怪しい見知らぬ悪徳業者だけではありません。むしろ、本当の危険は日常生活の中に潜んでいます。
最初は親切な手伝いや世間話から始まり、少しずつ信頼関係を築いていく。そして、相手が完全に心を許した段階で、徐々に金銭的な要求を始める。このような計画的な「グルーミング」を経て、日常的に家に出入りする宅配業者、介護ヘルパー、信頼していたタクシーの運転手、長年の知人などが、ある日突然、加害者に変貌するのです。「まさかあの人が」と家族が気づいた時には、すでに手遅れになっているケースが後を絶ちません。
社会問題化する「高齢者の経済的虐待」
本人の同意なく財産を不当に処分したり、利益を得たりする行為は「経済的虐待」と呼ばれ、高齢者虐待防止法でも禁じられている深刻な人権侵害です。この問題の根深さは、加害者が外部の人間だけでなく、実の子や甥・姪といった親族であるケースも少なくない点にあります。「生活費の面倒を見ているのだから」「将来相続するのだから」といった身勝手な論理で、年金や預貯金を使い込む行為も、紛れもない虐待です。これはもはや個別の家庭の問題ではなく、社会全体で向き合うべき喫緊の課題となっています。
具体的な搾取の事例紹介――2,000万円が2年で50万円に
ここで、実際にあった痛ましい事例をより詳しくご紹介します。夫に先立たれ、障害のある妹さんと二人で暮らしていた80代のA子さんの身に起きた出来事です。
食料品や生活用品の過剰販売
A子さんのもとには、顔なじみの食品配達業者が頻繁に出入りしていました。その業者は、A子さんの認知症を知りながら、「妹さんの分も買っておきましたよ」「これは体にいいから」と、二人暮らしには到底消費しきれない量の食料品を届け続け、高額な代金を請求。専門家が家を訪れた時、そこには手つかずのまま腐敗した食品の山と、異臭が広がっていました。
タクシー運転手による不透明な金銭要求
外出の際に頼りにしていたタクシー運転手は、A子さんの信頼を悪用しました。旅行の付き添いでは自身の配偶者の分まで旅費を支払わせ、病院への送迎の際には銀行に立ち寄り、100万円を引き出させ、そのうちの50万円の使途が不明となっていました。後日、タクシー運転手に問いただしても、知らないというばかりで終始否定していました。
通帳履歴に残る不自然な引き出し
親族がA子さんの通帳を確認したところ、2,000万円以上あったはずの預金が、わずか2年で50万円にまで減少していました。通帳には、上記以外にも多数の使途不明な高額出金が記録されており、それはA子さんが静かに、しかし確実に財産を蝕まれていた動かぬ証拠でした。
事後的な請求の困難さと法的ハードル
「騙し取られたお金なのだから、返してもらえばいい」と考えるのは当然です。しかし、一度失われた財産を法的に取り戻す道は、極めて険しいのが現実です。
「認知症と知らなかった」と主張された場合の限界
相手方に返金を求めても、ほとんどの場合、「本人が納得して支払った」「認知症だとは知らなかった」と主張されます。相手の悪意を証明することは非常に難しく、法廷では「契約当時に判断能力が著しく欠けていたこと」を医学的な証拠で示さなければならず、そのハードルは極めて高いのです。
証拠不足による立証の難しさ
裁判で請求が認められるためには、被害者側が「不当な取引であったこと」を客観的な証拠で証明(立証)しなければなりません。例えば、契約時の録音や、相手の悪意を示すメール、第三者の証言などが必要になりますが、用意できるケースは稀です。証拠がなければ、たとえ状況的にどれだけ疑わしくとも、裁判所は請求を認めてはくれません。
上記の例でも、タクシー運転手についても、実際にいくらタクシー業者に支払われたのか記録がなく(敢えて記録を残していない)、上記の引き出した100万円のうちの50万円についても、タクシー運転手が「もらっていない」と言えば、そのほかに証拠がありません。高齢者本人が途中で落とした可能性も理論的には考えられ、そのように言われてしまうと立証の方法がなく請求が困難です。
訴訟にかかる費用とリスク
仮に裁判に踏み切るとしても、弁護士の着手金や成功報酬など、多額の費用がかかります。数百万円を取り返すために、数十万円以上の費用を先に支払う必要があり、しかも長い時間をかけた末に敗訴すれば、財産は1円も戻ってこない「費用倒れ」という最悪の結果を招くリスクがあるのです。

予防法務としての見守り契約・財産管理契約・任意後見契約
被害に遭ってからでは手遅れになる可能性が高いからこそ、重要になるのが「予防法務」という考え方です。問題が起こる前に、法的な仕組みで財産を確実に守るための3つの契約をご紹介します。
見守り契約――日常生活の異変を早期に察知
弁護士が定期的にご本人と面会や連絡を取り、生活状況に変化がないかを確認する契約です。もしA子さんがこの契約を結んでいれば、弁護士が定期訪問の際に家の異変に気づき、早い段階でご家族に報告することで、被害の深刻化を防げた可能性があります。これは、離れて暮らす家族にとっての「外部の目」となる重要なセーフティネットです。
財産管理契約――不要な出費を防ぎ、資産を守る
ご本人の判断能力はしっかりしていても、金銭管理に不安がある場合に、その財産管理を弁護士に委託する契約です。もしA子さんがこの契約を結んでいれば、高額な支払いはすべて弁護士の承認が必要になるため、過剰な商品の購入代金や、タクシー運転手への不透明な支払いは、そもそも発生しませんでした。財産へのアクセスを物理的にブロックする、強力な防波堤となります。
任意後見契約――判断能力が低下した後の安心対策
将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備え、「誰に」「何を支援してもらうか」をご本人が元気なうちに自らの意思で決めておく、公正証書で作成する契約です。判断能力が低下した後は、ご自身が指定した弁護士(任意後見人)が、家庭裁判所の監督のもとで財産を保護・管理します。公的な裏付けがあるため、最も確実で安心な将来への備えと言えます。
弁護士に依頼することのメリット
これらの契約を弁護士に依頼する最大のメリットは、その「客観性」と「専門性」です。家族がお金の管理をすると、他の親族から「使い込んでいるのでは?」と疑われ、新たな争いの火種になることがありますが、職業倫理と守秘義務を負う弁護士が第三者として関わることで、そのような親族間トラブルを防ぎます。法的知識に基づいた適切な対応で、ご本人の財産と家族の平穏の両方を守ることができるのです。
まとめ――高齢者の財産と尊厳を守るために
事後対応よりも事前対策が重要
ここまで見てきたように、一度発生してしまった金銭被害を回復することは極めて困難です。大切なのは、問題が起こってから慌てる「事後対応」ではなく、問題が起こらないように先手を打つ「事前対策」に他なりません。
契約を通じて高齢者を搾取から守る仕組みを整える
見守り契約、財産管理契約、そして任意後見契約は、単なる事務的な手続きではありません。これらは、判断能力が低下した高齢者を社会の搾取から守り、その人らしい穏やかな生活と人間としての尊厳を維持するための、法的な「仕組み」なのです。
まずは弁護士への相談から始めましょう
「うちの親は大丈夫だろうか」「親にどう切り出せばいいか分からない」そう感じている今が、行動を起こす最適なタイミングです。これらの対策の話は、親の能力を疑うものではなく、「将来の安心を親子で一緒に作るための、前向きな対話」です。どうか一人で抱え込まず、専門家である弁護士にご相談ください。その一歩が、あなたの大切な家族を守るための最も確実な方法です。
任意後見制度や見守り契約等の導入をご検討中の方は、お気軽に法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に法的サービスを提供しております。当事務所では、任意後見・見守り・遺言・死後事務委任等に関する初回相談を無料で承っております。認知症対策、相続対策、事業承継対策など、あなたの悩みに合わせた最適なプランをご提案いたします。「任意後見」についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
早めの準備がトラブルを防ぎます。あなたの大切な生活を守るための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
併せて読みたいオススメ記事