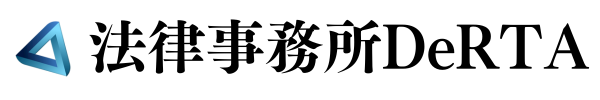【弁護士が解説】将来型・移行型・即効型とは?任意後見契約の類型を徹底比較

はじめに:超高齢社会を生きる私たちに「任意後見契約」が必要な理由
平均寿命が延び、人生100年時代と言われるようになった現代。誰もが自分らしく、安心して老後を過ごしたいと願っています。しかし、高齢化が進むにつれて、認知症などで判断能力が不十分になるリスクも高まっています。
「まだ自分は元気だから大丈夫」と思っていても、いつ何が起きるかは誰にもわかりません。そのような「もしも」の時に備え、ご自身の財産や生活をどのように守っていくかを、元気なうちに決めておくことが重要です。そのための最も有効な手段の一つが「任意後見契約」です。
この記事では、ご自身の状況や希望に合わせて選べる、**任意後見契約の3つの類型(将来型・移行型・即効型)**について、弁護士がわかりやすく解説します。
1. そもそも任意後見契約とは?法定後見制度との違い
**「任意後見契約」**とは、将来、ご自身の判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめご自身が選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理や身上監護に関する事務を任せるための契約です。具体的には、預貯金の管理や医療・介護サービスの契約、施設入所の契約などを任せることができます。この契約は、公正証書によって結ばれるため、法的な効力と安全性が確保されています。
国が後見人を選ぶ法定後見制度と異なり、任意後見契約では、ご本人の意思が尊重される点が大きな特徴です。信頼できる家族や友人、あるいは専門家を、ご自身の「未来のパートナー」として指名できるため、より安心感の高い老後設計が可能となります。ご本人の希望に沿った形で、後見の内容や報酬についても細かく設定できるため、画一的な法定後見よりも柔軟な対応が期待できます。
2. 任意後見契約の3つの類型|それぞれの特徴を理解しよう
任意後見契約には、ご本人の現在の状況や、将来への備えに対する考え方に応じて使い分けられる、主に3つの利用形態があります。それぞれの類型は、契約を締結するタイミングと、実際に後見が開始されるまでのプロセスが異なります。
- 将来型: 元気なうちに契約を結び、実際に後見が始まるのは、判断能力が不十分になった時。
- 移行型: 契約締結後すぐに財産管理などを始め、将来的に後見へ移行するタイプ。
- 即効型: 契約締結と同時に後見を開始するタイプ。
この3つの類型を理解することが、あなたに最適な任意後見契約を選ぶための第一歩です。ご自身のライフプランを具体的に描きながら、どの類型が最も適しているかを考えてみましょう。
3. 将来型任意後見契約:見守り契約と合わせて備える、安心の将来設計
将来型は、将来、認知症になった場合に備えて安心のために任意後見契約を締結する類型です。今は後見の必要はないが、もしもの時に備えて信頼できる人を決めておきたい、という方に向いています。契約締結後、ご本人の判断能力が不十分になったと判断された時点で、家庭裁判所への申立てを経て後見が開始されます。
この類型では、見守り契約と合わせて利用することが一般的です。見守り契約とは、任意後見人が定期的にご本人と連絡を取り、健康状態や生活状況を確認するものです。これにより、後見を開始すべきタイミングを逃さずに察知できますし、いざ後見が始まるときもスムーズな移行が可能です。
将来型任意後見契約のメリット
- ご自身の意思で決められる: 判断能力が十分にあるうちに、ご自身の意思で後見人や後見事務の内容を自由に決められるため、将来の不安を大きく軽減できます。
- 将来の変化を早期に察知: 見守り契約を併用することで、ご本人の状況の変化を早期に把握し、適切なタイミングで後見をスタートできます。
- 費用負担を抑えられる: 後見が始まるまでは、見守り契約の報酬だけで済むため、移行型や即効型に比べて費用負担が軽い傾向にあります。
将来型任意後見契約のデメリット
- 本人の状況を把握する必要がある: 後見が始まるまでにタイムラグがあるため、定期的に本人の状況を把握し、認知能力の低下の有無を確認する必要gああります(そのために見守り契約を締結するのが通常です。)。
- 契約を忘れてしまう: 契約を結んだ安心感から、その存在を忘れてしまい、いざという時に手続きがスムーズに進まないことも考えられます。
4. 移行型任意後見契約:財産管理委任契約から後見へスムーズに移行
移行型は、契約締結後すぐに、任意後見人となる予定の人に財産管理委任契約を依頼し、ご本人の判断能力が低下した段階で任意後見契約を発効させる利用形態です。この類型は、将来型と即効型の中間的な位置づけと言えます。
例えば、「今は元気だが、銀行の手続きが面倒になってきた」「将来の入院費の管理を任せたい」といった場合、財産管理を委任し、将来の判断能力に問題が生じた段階で、後見へのスムーズな移行を可能にします。これにより、ご本人の現在の生活をサポートしつつ、将来の備えも同時に進められます。
移行型任意後見契約のメリット
- 継続的な支援を受けられる: 後見が始まる前から、継続的に支援を受けられるため安心感が高いです。日々の財産管理や生活上のサポートを頼めるため、ご本人の負担が軽減されます。
- 信頼関係を築ける: 将来後見人となる人と、早期から関係性を築けるため、いざという時も安心して任せられます。
- 財産管理の手間が省ける: 日常的な財産管理を任せられるため、ご本人の負担が軽減され、より自由に時間を使えます。
移行型任意後見契約のデメリット
- 費用負担が大きい: 財産管理や見守り期間中も報酬が発生するため、将来型に比べて費用負担が大きくなります。
- 任意後見監督人選任の申立てがなされないケースがある: 任意後見をスタートさせる必要であるところ、そのまま財産管理を進めても不都合はないとして、本来であれば任意後見監督員の監督を受けるべきところ、これがなされないという問題もあります。
- 信頼する人に任せる必要がある: 財産管理委任契約は財産管理という重要な事項を他人に依頼するものでありため、信頼できる人に任せる必要があります。また、契約内容も権限を濫用されないように慎重に決定する必要があり、専門家の判断も必要です。
5. 即効型任意後見契約:即時に後見をスタートさせるスピーディーな選択肢
即効型は、任意後見契約の締結と同時に後見を開始する利用形態です。すでに判断能力が不十分になっており、すぐにでも財産管理や契約行為の代理が必要な場合に選択されます。この類型は、主に病気や事故などで急に判断能力を失ってしまった場合に利用されます。
ただし、この類型を選択するには、契約を締結する際に、ご本人が契約内容を理解し、その意思を表明できる必要があります。この点が、すでに判断能力を失っている方が利用する法定後見制度との大きな違いです。法定後見は、ご本人の意思能力がなくても申立てが可能ですが、任意後見はあくまでご本人の意思に基づいて行われる契約であるため、この点が大きなポイントとなります。
そのため、即効型の利用は慎重に判断すべきという見解も多く、たとえば、本人が受任者を特に信頼している場合や、他の親族の介入を嫌がっている場合等の例外的なケースにのみ認めるべきとする見解や、本人が積極的な意思を有していて自分の希望を反映させる意欲をもち積極的に検討を行っている場合に限定すべきとする見解もあるところです。これが認められない場合には、補助開始の審判等を求めることになります。
即効型任意後見契約のメリット
- 迅速な対応が可能: 必要な時に、速やかに後見を開始できます。家庭裁判所への申立て後、すぐに後見監督人選任の手続きが進行します。
- ご本人の意思が反映される: 法定後見制度に比べて、ご本人の意思が反映されやすいです。後見人や後見事務の内容を自分で決められるため、納得感の高い支援を受けられます。
- 後見人選任手続きが不要: 契約締結後、家庭裁判所に後見監督人選任の申し立てをすれば、すぐに後見がスタートできます。
即効型任意後見契約のデメリット
- 利用できる条件が限られる: ご本人が契約内容を理解できる状態でないと利用できません。意思能力の有無について、公正証書を作成する際に、公証人から医師の診断書の提出を求められるケースもあります。
- 準備期間が少ない: すぐに後見が始まるため、契約内容や後見人の選定について十分に検討する時間が少ない可能性があります。後見人との信頼関係を築く時間的な余裕もないという問題もあります。
- 判断能力の有無が争点になる: 後見開始後、契約時の判断能力について争いが生じるリスクがあります。
まとめ: あなたに最適なのはどれ?各類型を徹底比較

ご自身の未来に合わせた任意後見契約を
どの類型を選ぶべきかは、ご自身の現在の状況と将来に対する考え方によって異なります。
将来型は、まだ心身ともに元気で、将来のために計画的に備えたい方に向いています。もしもの時の安心を確保しつつ、今すぐの費用負担を抑えたい場合に適しています。見守り契約を併用することで、後見が始まるタイミングを適切に判断できる安心感があります。
一方、移行型は、今は元気でも、すぐに財産管理などの支援を始めてもらいたいと考える方に最適です。日々の生活のサポートを求めながら、将来の備えも同時に進めたい場合に適しています。財産管理委任契約から後見へと段階的に移行することで、継続的なサポートを受けられます。
そして、即効型は、すでに判断能力に不安があり、すぐにでも後見を始めたいという方に適しています。急な病気や事故で判断能力に支障が生じたものの、まだ契約できる程度の意思能力がある場合に有効な手段です。ただし、契約内容を理解できる状態であることが前提となります。
任意後見契約は、ご自身の将来を安心して過ごすための、非常に有効な手段です。どの類型が最適かは、現在の状況や将来への希望によって異なります。
当事務所では、弁護士がお客様一人ひとりの状況を丁寧に伺い、最適な任意後見契約の類型や、見守り・財産管理委任契約の活用方法についてアドバイスいたします。
弁護士に相談して安心・確実な契約を
任意後見契約は、ご自身の人生の終盤を支える、非常に重要な契約です。任意後見契約の設計でお悩みの方は、ぜひ法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。
当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に法的サービスを提供しています。
複数受任者の活用や、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約との組み合わせなど、将来の不安を解消するためのオーダーメイドの提案が可能です。初回相談は無料で承っております。
任意後見についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
併せて読みたいオススメ記事