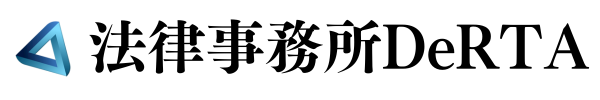【超初心者向け】遺言はなぜ必要? 相続でもめないための基礎知識

本記事ではは遺言がなぜ必要か?について全くの初心者の方に、遺言がなぜ必要かのイメージをもっていただくために、細かいことは抜きにしてできるだけ簡単に説明したいと思います。
自分の財産を、愛する家族や大切な人にのこしたい。その想いをかなえる一番の方法が「遺言」です。「うちはお金持ちじゃないから」「家族の仲が良いから大丈夫」と思っている方もいらっさはるかもしれません。
実は、遺言は特別なものではなく、残された家族を困らせないための、思いやりの準備です。この記事では、遺言の基本から、なぜ必要なのかを、誰にでも分かるように解説します。
遺言とは?なぜ必要かを知る前の一番やさしい基本のキ
遺言とは、ひと言でいえば「あなたの財産分けの希望を記した、家族へのメッセージ」です。
きちんと作れば、ただのメッセージではなく法的な力を持つので、あなたの想いを確実に実現できます。遺言をのこすことは、残された家族が「もめない」ためのお守りのようなものです。
遺言書でできること(例)
- 財産をあげる相手や、その割合を自由に決められる。
- 「この家は妻に」というように、財産ごとに渡す人を指名できる。
- お世話になった友人など、家族以外の人にも財産をのこせる。
- 面倒な手続きの担当者を、あらかじめ決めておける。
遺言書が一番パワフル
相続では、遺言書の内容が法律のルールより優先されます。
あなたの「こうしてほしい」という想いが、一番大切にされるということです。
ただし、配偶者や子どもなど、ごく近しい家族には「最低限もらえる権利(遺留分)」だけは残ります。これは家族の生活を守るための、小さな決まりごとです。
遺言はなぜ必要?知っておきたい4つの理由
遺言をつくることには、具体的にどんないいことがあるのでしょうか。ここでは、特に大切な4つの理由を、より詳しくご紹介します。
1.家族のケンカ(争族)を防げる
遺言がない場合、相続人全員で「誰が、何を、どれだけもらうか」を決める遺産分割協議という話し合いをしなければなりません。これが、一番もめやすいポイントです。
例えば、「私が親の面倒を一番見てきたから、家は私がもらうべきだ」「いや、兄さんは昔、親からお店の資金を出してもらったじゃないか」など、過去の不満が噴出したり、それぞれの家庭の事情が絡み合ったりして、話し合いがまとまらないケースは後を絶ちません。
遺言書で、あなたが「家は妻に、預金は長男と次男で半分ずつ」というように、明確な分け方を指定しておけば、そもそも話し合いをする必要がなくなります。残された家族が、お金のことでいがみ合う悲しい事態を避けることができるのです。
2.相続手続きの負担が、驚くほど軽くなる
人が亡くなると、銀行預金の解約や不動産の名義変更など、様々な手続きが必要になります。遺言がないと、これらの手続きを進めるために、まず「相続人は誰なのか」を証明しなくてはなりません。それには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書などを集める必要があります。相続人が多かったり、遠方に住んでいたりすると、これだけでも大変な時間と労力がかかります。
遺言書があれば、こうした膨大な書類集めを大幅に省略できます。特に、手続きの担当者(遺言執行者)を指定しておけば、その人が代表して手続きを進められるため、相続人それぞれの負担が劇的に軽くなります。
3.あなたの「特別な想い」を形にできる
法律で決められた相続人(法定相続人)は、配偶者や子どもなど、ごく限られた範囲の人のみです。しかし、あなたの人生には、他にも大切な人がいるかもしれません。
例えば、「学生時代、苦しい時に助けてくれた友人に、感謝のしるしをのこしたい」「孫の大学の入学資金にしてほしい」「長年連れ添い、介護もしてくれた長男の嫁にも財産を分けたい」。こうした相続人以外への想いは、遺言がなければ実現できません。
また、「この絵画は、価値をよく分かってくれている〇〇に」「事業は、才能のある次男に継がせたい」など、財産の価値やあなたの事業への想いを、一番ふさわしい人に託すことができます。遺言は、法律の枠を超えて、あなたの人生の物語を伝えるためのツールなのです。
4.残された家族の「これからの生活」を守れる
遺言の最も大きな役割の一つが、残された家族の生活基盤を守ることです。
特に重要なのが、ご自宅の相続です。例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人だったとします。遺言がないと、妻も子どもたちも家の所有権を分け合うことになります。もし、子どもたちのどちらかが「自分のお金(相続分)が欲しいから、家を売って現金で分けてほしい」と言い出したら、最悪の場合、残された妻は住み慣れた家を失うことになりかねません。
遺言書に「自宅不動産は、妻に相続させる」と、はっきりと書いておけば、そのような心配は一切なくなります。配偶者に、安心して穏やかな日々を送り続けてもらうために、遺言は絶大な力を発揮するのです。
こんな人は特に遺言を!遺言がなぜ必要かを具体的なケースで考えよう
遺言はすべての人におすすめですが、特に次のような方は、作っておく必要性が高いと言えます。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
子どものいないご夫婦の場合
お子さんがいない場合、もし夫が亡くなると、相続人は「妻」と「夫の両親(または祖父母)」になります。もし両親がすでに他界している場合は、「妻」と「夫の兄弟姉妹(や甥姪)」が相続人です。遺言がないと、長年連れ添った妻が、夫の兄弟たちと遺産分割の話し合いをしなければならず、最悪の場合、住み慣れた家を売ってお金で分けなくてはならない…という事態も起こりえます。「全財産を妻(夫)に」という一文を遺言でのこしておけば、パートナーは安心して生活を続けられます。
事実婚(内縁)のパートナーがいる方の場合
婚姻届を出していないパートナーには、法律上の相続権は一切ありません。どれだけ長く一緒に暮らし、生計を共にしていても、遺言がなければ財産を1円ものこすことができません。残されたパートナーの生活を守るためには、「パートナーに財産を遺贈する」という遺言書が絶対に必要です。
再婚していて、前の配偶者との間に子がいる方
前の配偶者との間の子どもにも、今の配偶者との間の子どもと全く同じ相続権があります。遺言がないと、現在の家族と、普段は交流のない前の家族の子どもとが、財産分けの話し合いをすることになります。感情的な対立も生まれやすく、話し合いが非常に難航するケースが多いです。遺言でそれぞれの取り分を明確に指定しておくことが、円満な解決への第一歩です。
会社やお店を経営している方
会社の株式や、事業で使っている土地・建物などが相続財産になります。遺言がないと、これらの財産が法定相続のルールで複数の相続人に分散してしまい、後継者が経営に必要な議決権を確保できなかったり、事業用の土地を失ったりする危険があります。事業をスムーズに次世代へ引き継がせるために、遺言による事業承継の準備は必須です。
財産のほとんどが家や土地という方
相続財産が現金や預貯金であれば、金額で平等に分けやすいのですが、不動産はそうはいきません。不動産が複数ある場合は誰がどれを取得するのか、売却してわけるのかどうないのか等の問題が発生しますので、「誰が家を継ぐのか」「どうやって公平に分けるのか」で必ずと言っていいほどもめます。遺言で「自宅は長男に」と指定し、その代わりに他の相続人には現金を渡す(代償分割)といった具体的な分け方を指示しておくことで、争いを防げます。
障害のあるお子さんがいる方
「自分が亡くなった後、この子の生活はどうなるのだろう」と心配されている方も多いでしょう。遺言で、障害がある子の生活を支えるために他の兄弟より多めに財産をのこしたり、信頼できる親族や専門家(弁護士など)に財産の管理をお願いする旨を記したりすることで、親亡き後の安心につなげることができます。
いわゆる「おひとりさま」の方
配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹もいない場合、何もしなければ財産は最終的に国のものになります。「お世話になったあの人に」「応援しているNPO法人に寄付したい」という想いがあるなら、遺言書を作成して、あなたの財産の行き先を自分で決める必要があります。
親の面倒を見ているお子さんがいる方
特定の子供が親と同居して介護をしたり、生活の援助をしたりしている場合、その貢献は法律の相続分には自動的に反映されません。他の兄弟姉妹と同じ取り分では不公平だと感じることもあるでしょう。「長年面倒を見てくれた長女に、感謝の気持ちとして多めにのこしたい」という親の想いを形にするには、遺言書が最も有効な手段です。
子どもたちの経済状況に差がある方
子どもたちがそれぞれ独立しても、経済的に余裕のある子もいれば、少し苦しい生活をしている子もいるかもしれません。「住宅ローンの返済が大変な次男を、少しでも助けてやりたい」。そんな親としての愛情も、遺言があれば、法定相続分に上乗せして財産をのこす、といった形で実現できます。

さっそく準備!分からないことは弁護士に相談しよう
遺言を作ろうと思ったら、まずは身の回りの整理から始めましょう。
- 自分の財産をリストアップする預貯金、家、土地、株など、何がどこにどれだけあるか書き出してみましょう。
- 誰にのこしたいか考える財産を渡したい相手と、その分け方を大まかに決めていきます。
遺言書には、自分で書く簡単なもの(自筆証書遺言)と、公証人に作ってもらうもの(公正証書遺言)があります。自分で書くものは手軽ですが、書き方を間違えると無効になる危険も。より確実なのは、公正証書遺言です。
もし内容が複雑だったり、絶対に失敗したくなかったりする場合は、弁護士などの専門家に相談するのが一番の近道です。弁護士に頼めば、無効にならない、ちゃんとした遺言書を作ってもらえますし、将来のトラブルを見越した最適な分け方をアドバイスしてくれます。
遺言でお悩みの方は、ぜひ法律事務所DeRTA(デルタ)へご相談ください。
当事務所は、東京都港区西新橋に所在し、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に法的サービスを提供しています。
遺言のほかに、高齢者向けのメニューとしえ、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約との組み合わせなど、将来の不安を解消するためのオーダーメイドの提案が可能です。初回相談は無料で承っております。
さらに詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
併せて読みたいオススメ記事